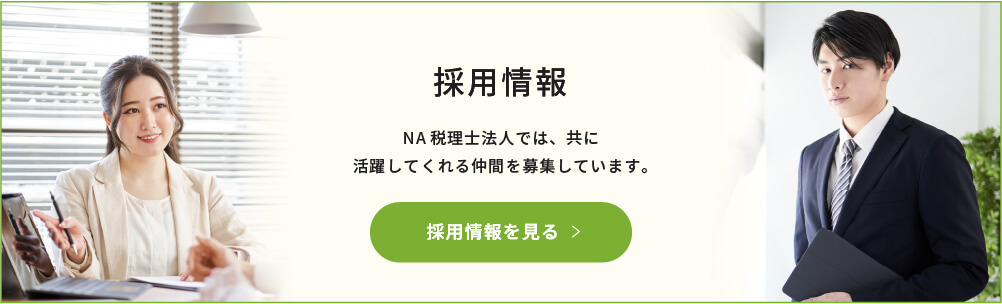全てはお客様の
成長のために
会計の知識がなくても大丈夫。
最初は、何に困っているのかをお聞かせください。
経営に関することならどんな事でも、
プロとして、人として、お客様と一緒に考え
サポートします。



サービス紹介
税理士法人のサービスについてご紹介いたします。
お気軽にご相談ください。
お役立ち情報
-
贈与・贈与税
相続・贈与・相続税の違いとは
相続とは、個人の死亡により開始し、財産と債務の両方が移転します。手続きなしに、全財産が自動的に相続人に受け継がれます。贈与と...
詳しく見る
-
相続関係資料
相続関係資料の作成
相続税の申告においては、戸籍、土地・建物の登記簿謄本等様々な書類を取得する必要性に加え、作成しなければならない書類が多数ありま...
詳しく見る
-
相続税 かかる財産・かからない財産
相続税のかかる財産・かからない財産
Ⅰ 相続税のかからない財産とは 1.墓地、墓石、仏壇など 墓地、墓石や仏壇などは、価値判断が難しい部分もあり...
詳しく見る
-
相続税の計算
相続税の計算には、大きく分けると、三段階があります。
Ⅰ 課税価格の計算方法 相続や遺贈により財産を取得した人の各々の財産の総額を個別に計算します。 相続又遺贈により...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
8月の税務労務スケジュール
8月の主な税務・労務スケジュール 本記事では、8月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。税務...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
7月の税務労務スケジュール
7月の主な税務・労務スケジュール 本記事では、7月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。税務...
詳しく見る
-
社会保険
算定基礎届・年度更新について
Ⅰ 社会保険の算定基礎届とは 健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
6月の税務労務スケジュール
6月の主な税務・労務スケジュール 本記事では、6月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。税務...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
【103万円の壁】の現在地
Ⅰ はじめに 令和7年度改正による「所得税」の「控除」に関する主な変更点は、 令和7年2月4日に国会に提出された...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
5月の税務労務スケジュール
5月の主な税務・労務スケジュール 本記事では、5月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。税務...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
税効果会計
Ⅰ 税効果会計とは 企業会計と税務会計は、計算目的の違いから一時的なズレ(タイミングの違い)が生じます。税効果会計とは、...
詳しく見る
-
事業承継
【親族内承継】とは
Ⅰ 【親族内承継】とは 親族内承継とは、現経営者の子供や孫、兄弟など親族に会社を引き継ぐ承継方法です。 第三者へ...
詳しく見る
-
競馬と確定申告
Ⅰ はじめに 競馬を楽しんでいますか。日本において、競馬は違法ではありません。しかし、ギャンブルという側面からどうしても...
詳しく見る
-
確定申告
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて
1.概要 国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、...
詳しく見る
-
福利厚生費
iDeCo+(イデコプラス)とは
個人の年金制度として人気の高いiDeCo(個人型確定拠出年金)ですが、従業員加入のiDeCoに、企業側が上乗せ拠出できる制度が...
詳しく見る
-
会社設立
非営利型一般社団法人による診療所設立のメリット
医業を行う個人事業主が法人化する場合、一般的には医療法人を設立することが多いですが、近年は一般社団法人がクリニックを開...
詳しく見る
-
事業承継
事業承継とは
はじめに 事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。具体的には経営権のほか、株式等の会社の資産や事業に関...
詳しく見る
-
確定申告
財産債務調書の提出義務
Ⅰ 財産債務調書とは 一定の所得金額および財産価額に達している人が、確定申告書とは別に提出しなければならない法...
詳しく見る
-
口座凍結について
「口座凍結」という言葉は...
詳しく見る
-
事業承継
事業承継税制と相続時精算課税制度の併用適用
はじめに 従来、事業承継税制と相続時精算課税制度は併用適用することが出来ませんでしたが、平成29年度税制改正によりその併...
詳しく見る
-
社会保険
「マイナ保険証」活用してますか?
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が廃止となり、保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)に引き継がれま...
詳しく見る
-
確定申告
暗号資産(仮想通貨)にかかる税金と確定申告について
はじめに ビットコイン(BTC)などの暗号資産(仮想通貨)は、投資対象として多くの関心を集めています。「投資で利益を得た...
詳しく見る
-
確定申告
外貨取引における為替差損益
最近の為替相場は、さまざまな要因によって影響を受け不安定な状況が続いていますが、円預金より高い金利が得られる外貨預金で将来のた...
詳しく見る
-
消費税
2割特例の適用範囲
Ⅰインボイス制度のおさらい インボイス制度は、消費税の標準税率10%と軽減税率8%が混在する複数税率制度のもと、売手側と...
詳しく見る
-
相続税
今すぐできる相続対策とは?
Ⅰ 2024年の税制改正による影響 2024年の税制改正では相続税・贈与税関連の法律が大幅に変わりました。詳細はこちらに...
詳しく見る
-
人事採用給与計算
労働条件の明示事項
Ⅰはじめに 2024年4月1日より法改正に伴い労働条件の明示事...
詳しく見る
-
消費税の確定申告
外国法人の消費税の納税義務
はじめに 外国法人が日本国内で法人税の課税の対象となる取引を行えば、当然法人税が課税されることとなりますが、たと...
詳しく見る
-
7月の税務スケジュール
色とりどりの紫陽花に、梅雨の訪れを感じる季節となりました。7月の主な「税務・申告に関するスケジュール」を掲載しております。税務...
詳しく見る
-
NA税理士法人の一日
はじめに 税理士法人は多くの人々にとって謎めいた場所です。 そこで、今回はNA税理士法人の一日を覗いてみましょ...
詳しく見る
-
遺言
ペットに相続は出来るか
Ⅰ ペットへの相続 飼い主にもしものことがあった際、ペットに財産を相続させることはできるのでしょうか。ペットの法的解釈と...
詳しく見る
-
相続が発生した方
相続登記の申請義務化
2024年4月1日より、不動産所有権に関する相続登記の申請義務化が始まりました。すでに多くの媒体で取り上げられているため、目に...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
地価公示価格
Ⅰ はじめに 3月末に令和6年度の地価公示価格が発表されました。令和6年は3年に一度の固定資産評価額の評価替えの年でもあ...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
令和6年分所得税・住民税の定額減税
定額減税について、 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。 今後、税制改正法案が成立し...
詳しく見る
-
確定申告
確定申告が始まっています。
はじめに 確定申告書の受付が始まっています。 令和5年(2023年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は...
詳しく見る
-
確定申告
令和5年分確定申告の効率化
Ⅰ 令和5年分確定申告でリリースされるe-Taxの新機能 令和5年分確定申告より、確定申告書等作成コーナーで下記1.のサ...
詳しく見る
-
社会保険
退職代行サービスについて知っておきたいこと
Ⅰ はじめに 自己都合退職の法的なルール 近年、従業員の代わりに退職連絡を請け負う「退職代行サービス」が増えています...
詳しく見る
-
社会保険給与計算
社会保険の年収の壁について
配偶者の扶養内で働いているパート従業員が就業調整を意識する「年収の壁」について、 2023年10月に「年収の壁・支援強化パッケ...
詳しく見る
-
会社設立
医療法人とは
個人事業主の方であれば法人化を検討される方も多くいらっしゃると思いますが、事業内容が「医業」である場合、つまり、ドクタ...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
令和6年1月からの電子取引データ保存
今年10月からインボイス制度が始まり、現場は日々対応に追われ混乱しています。 そんな中、来年1月からは電子帳簿保...
詳しく見る
-
年末調整
年末調整手続きの電子化
今年も年末調整の時期になりました。 まだ紙で従業員から申告書を提出してもらっている事業所が多いのではないでしょうか。 各種申告...
詳しく見る
-
人事採用
人手不足時代の採用戦略
はじめに 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)の減少が続く中、人手不足が経営と直結する状況になりつつあります。中小企業に...
詳しく見る
-
消費税
電子インボイスによる経理業務の効率化
Ⅰ 概要 10月1日から、インボイス制度が始まりました。制度開始に伴い、記帳業務が煩雑になるため、今後記帳に要する手間や...
詳しく見る
-
給与計算
令和5年度の地域別最低賃金
今年度の都道府県ごとの最低賃金が決定され、全国平均額は1,004円となり初めて1,000円を超えました。 東京都については20...
詳しく見る
-
退職金
退職金の法的性格(裁判事例を鑑みて)
飲酒運転により懲戒免職となった教員に対する退職金を巡る訴訟において、最高裁は退職金の支給を認めないとする判決を下した。 長年勤...
詳しく見る
-
社会保険
育児・介護休業法の改正
はじめに・・・ 少子化の進行は、人口の減少と高齢化を通じて社会経済に多大な影響を及ぼします。 2022年には合計特...
詳しく見る
-
消費税
適格請求書発行事業者になるかならないかの選択
2023年10月から開始されるインボイス制度に向け、仕入税額控除を受けるためには登録申請手続きを行う必要がありますが、比較的小...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
修正申告・更正の請求
修正申告・更正の請求は法定申告期限後に、計算違いなど申告内容の間違いに気が付いたときに行う手続きです。 Ⅰ修正申告とは ...
詳しく見る
-
令和5年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内
令和5年4月に、厚生労働省から「令和5年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内」が公開されました。 簡略版と詳細版があり...
詳しく見る
-
個人 融資
クラウドローンのご紹介
弊所はクラウドローン株式会社様と業務提携を致しました。 クラウドローンとは、利用者が希望する融資に合わせて、...
詳しく見る
-
年末調整
源泉徴収制度について
Ⅰ 源泉徴収制度の意義 所得税は、納税者自身がその年の所得金額と税額を計算の上、自主的に申告して納付する「申告納税制度」...
詳しく見る
-
消費税
リバースチャージ
Ⅰ リバースチャージとは 消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行...
詳しく見る
-
会社設立
法人名義の銀行口座
登記も完了し、「さぁこれから事業を始めよう」と思われている起業家の皆さんも多いと思いますが、 会社設立後に振込等の資金移動のた...
詳しく見る
-
社会保険
労働保険料の納付
Ⅰ 労働保険とは 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。 加入などの各種手続きを労災保険は労...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
増資・減資とは
Ⅰ 増資とは 増資とは、資金調達のために新株を発行するなどして資本金を増やすことをいいます。 増資によるメリットは...
詳しく見る
-
相続税の計算
相続税の時価と財産評価
相続人が被相続人から相続や遺贈で受け取った財産には相続税が課税されます。財産は時価に基づいて評価されるということが相続...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
みなし贈与にご注意!
Ⅰ.はじめに 個人から年間110万を超える財産の受取があった場合、受け取った側の個人が、の3月15日までに申告・納税...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
バーチャルオフィスとは
Ⅰ バーチャルオフィスとは バーチャルオフィスとは事務所用の住所を貸し出すサービスです。 住所の貸し出しだけ行って...
詳しく見る
-
譲渡所得
租税特別措置法第 40 条の規定による承認申請書
個人が寄付金を支出した場合には、寄付金控除の適用があります。しかし、土地、建物などの財産を法人に寄付した場合には・・・ ...
詳しく見る
-
確定申告
副業収入がある方の確定申告について
Ⅰ 副業と現代について サラリーマンは通常、会社が行う年末調整のみでその年分の所得税の精算が完了するため、一定の場合を除...
詳しく見る
-
給与計算
給与のデジタル払い
買い物などで現金の代わりにスマホを使って支払いを済ませる「キャッシュレス決済」が急速に普及しています。 このキャッシュレ...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
数値で把握できる経営指標
経営指標とは会社の経営状態を数字であらわした指標のことです。融資の際の判断材料として使用されたり、自社を分析して経営課題や目標...
詳しく見る
-
相続が発生した方
配偶者居住権のメリット・デメリット
長年連れ添った配偶者を亡くすということは大きな悲しみを伴うものです。そのような中、残された配偶者が住みなれた家を出ていかなけれ...
詳しく見る
-
確定申告
医師・歯科医師の概算経費特例
医師又は歯科医師は、社会保険診療報酬が年5,000万円以下の年分について、「概算経費率」による所得計算を行うことができます。概...
詳しく見る
-
税務・会計用語集記帳代行
税理士に税務代行してもらうことのメリットとデメリット
事業を始めようと思った時に何から始めればよいのか、その相談先としてまず税理士に相談すれば良いという情報を得て、弊社にご面談に来...
詳しく見る
-
控除一覧
ふるさと納税 とは
最近では身近な人もふるさと納税をされる方が増えてきています。魅力的な返礼品も増えて、今年からふるさと納税を始めてみよう、とお考...
詳しく見る
-
消費税
棚卸資産に係る消費税額の調整
棚卸資産に係る消費税額の調整 Ⅰ 免税事業者が課税事業者となった場合 課税事業者となる日の前日において所有する棚卸...
詳しく見る
-
年末調整
令和4年分 年末調整について
Ⅰ 令和4年分 年末調整の変更点 そろそろ、令和4年分の年末調整の準備・スケジュールを考え始めている方もいらっしゃるので...
詳しく見る
-
社会保険
社会保険の適用拡大
2022年10月より、パート・アルバイトの方についての社会保険の適用が拡大されます。 社会保険は、原則としては週の労働時...
詳しく見る
-
消費税
インボイス制度Q&Aのご案内
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
欠損金の繰戻し還付とは
Ⅰ法人税法上の概要 この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額をその事...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
クラウド会計ソフトの概要
Ⅰ クラウド会計ソフトとは 会計ソフトとは、簿記のルールに基づいて会社で行われる取引の一つ一つを記録し、貸借対照...
詳しく見る
-
消費税
計算方法・課税期間・申告時期
Ⅰ 計算方法 消費税は、事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて「納付する消費税」を計算し納付します...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
法人税の確定申告の基礎知識
Ⅰ 法人税の確定申告の申告期限 1.原則は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。 2.災害があった場合や、会計...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
法人税の確定申告FAQ
Q1 法人税の計算は、決算書の利益に税率を掛けるんでしょうか? A1 いいえ。法人税の所得の金額に税率を掛けます。1.法...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
税務上の繰延資産とは
Ⅰ 税務上の繰延資産とは 法人が支出する費用で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものを、繰延資産と言います。さ...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
青色申告とは
Ⅰ 青色申告とは 青色申告とは、一定の要件を満たすことにより、青色申告書を用いて申告する手続きです。もともとが青色の申告...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
青色欠損金とは
Ⅰ 青色欠損金とは 青色欠損金とは、簡単に言ってしまえば、決算時に生じた赤字のことです。税法上この赤字を「欠損金」といい...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
賃上げ促進税制とは
Ⅰ 賃上げ促進税制とは 賃上げや人材育成への投資を積極的に行う法人が、雇用者に支払う給与等の支給額を一定割合以上増加させ...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
交際費とは
Ⅰ 交際費とは 交際費等とは、「交際費、接待費、その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
固定資産の特別償却・控除
Ⅰ 固定資産の特別償却とは 1. 特別な規定により、通常の減価償却を超えて償却費を計上すること 2. 規定の種類に...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
減価償却費とは
Ⅰ 減価償却費とは 事業などの業務のために用いられる資産(建物、建物付属設備、車両運搬具など)を取得した際は、その取得に...
詳しく見る
-
法人住民税
法人税割とは
法人税割は、法人税額を基として税率を乗じて法人住民税(法人税割)を計算します。 法人税額 × 法人住民税の税率 = 法人...
詳しく見る
-
法人住民税
法人住民税とは
1.申告納税先 法人に対しても、道府県民税と市区町村民税、すなわち住民税が課税され、これを一般には法人住民税といいます。...
詳しく見る
-
法人住民税
法人均等割とは
Ⅰ 均等割とは 1.法人均等割とは 市町村民税は、資本金等の金額と従業員数に応じて、都道府県民税は資本金等の金額に...
詳しく見る
-
法人事業税
法人事業税の非課税事業とは
Ⅰ 法人事業税の非課税事業とは 法人事業税の納税義務者は、原則として事業を行うすべての法人(公益法人等は、収益事業を行...
詳しく見る
-
法人事業税
法人事業税の税率表
下記URL(東京都主税局HP)をご確認ください。 URL:https://www.tax.metro.tokyo.lg....
詳しく見る
-
法人事業税
法人事業税の課税方式の見直しについて
これまで、電気供給業に係る法人事業税は「収入割」のみ適用されていましたが、令和2年度税制改正により、電気供給業のうち発電・小売...
詳しく見る
-
法人事業税
法人事業税とは
Ⅰ 地方税申告書とは 地方税申告書はどのようなものか。会社の利益(所得)に対しては、法人税の他に地方税が課されます。地方...
詳しく見る
-
法人事業税
分割法人の取り扱い
Ⅰ 分割基準とは 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人又は個人に対しては、その法人又は個人...
詳しく見る
-
法人事業税
所得割
Ⅰ 所得割とは 所得割とは、所得金額に対して事業税率を乗じて計算します。この場合の所得金額は、法人税別表4で算出される所...
詳しく見る
-
法人事業税
収入割
Ⅰ 収入割とは 電気供給業・ガス供給業・保険業など、所得金額を課税標準にするのは妥当ではない法人に課されるものです。収入...
詳しく見る
-
法人事業税
外形標準課税
Ⅰ 外形標準課税とは 外形標準課税は、従来の所得に対する事業税が課される法人(特別法人等の一定の法人を除きます)に対して...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
自己資本と他人資本とは
Ⅰ 資本とは 資本とは事業活動の元手となるお金のことです。 Ⅱ 自己資本とは 自己資本とは資本のうち、資本金...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
人件費とは
Ⅰ 人件費とは 人件費とは、人事関連費用の総額です。具体的には、給与賃金手当、賞与、福利厚生費(法定福利費と法定外福利費...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
費用収益対応の原則とは
Ⅰ 費用収益対応の原則とは 費用、収益対応の原則とは、期間収益とそれに関連する期間費用を対応させて、期間損益を計算する原...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
引当金とは
引当金の設定要件は下記4つを満たすことが前提となります。 ◆将来の特定の費用又は損失◆その発生が当期以前の事象に起因する...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
未払金と未払費用とは
Ⅰ 未払費用とは 未払費用とは、一定の契約に従い、”継続して”役務の提供を受ける場合、既に提供さ...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
仕入債務とは
Ⅰ 仕入債務とは 仕入債務とは、商品や材料の仕入などを購入し、支払いをすぐに行わず、後で支払うことを約束した債務のことで...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
資産(資産の種類)とは
Ⅰ 棚卸資産とは 在庫の事です。在庫の種類も、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品などがあります。 棚卸資産の貸借対...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
注記表とは
Ⅰ 注記表とは 注記表とは、企業の貸借対照表や損益計算表の財務諸表についての情報の補足事項をまとめたものを指します。会社...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
株主資本等変動計算書とは
Ⅰ 株主資本等変動計算書とは 貸借対照表の純資産の変動状況を表す財務諸表のことです。主に、会社の利益を何に使ったのかを知...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
製造原価報告書とは
Ⅰ 製造原価報告書とは 製造業が当期間に製造した製品の製造原価を記入した計算書類のことで、財務書表の一つとして損益計算書...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
B/SとP/Lの違い
貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)は、企業の財務状況を報告するための2つの重要な書類です。両者の目的と提供する情報には...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
損益計算書とは
Ⅰ 損益計算書とは、一定期間における企業の経営成績をまとめた表のことです。 費用、収益、それらを差し引きして出る利益の3...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
貸借対照表とは
Ⅰ 貸借対照表とは、一定時期における企業の財政状態をまとめた表のことです。 資産、負債、純資産の3つの項目が表記されてお...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
簿記・会計とは
Ⅰ 簿記とは 簿記とは主に複式簿記のことを指し、15世紀大航海時代のイタリアで複式簿記が出来上がったと言われています。貴...
詳しく見る
-
法人事業税
特別法人事業税とは
Ⅰ 特別法人事業税とは 令和元年度税制改正により、地方間の税収偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離し、国税である特...
詳しく見る
-
事業承継
事業承継の進め方
スムーズに事業承継を進めるためには、早期に準備に着手することが大切です。まずは、事業承継に向けた準備の必要性を認識してスタート...
詳しく見る
-
事業承継
事業承継で引き継ぐ対象
Ⅰ経営(人)の承継 事業承継における「経営の承継」とは「経営権」の承継をいいます。特に中小企業においては経営者個人にノウ...
詳しく見る
-
法人事業税
事業所税の仕組み
Ⅰ事業所税の仕組み 事業所等の床面積を対象とする資産割、従業者の給与総額を対象とする従業者割に分かれる。 1.事業...
詳しく見る
-
法人事業税
事業所税とは
Ⅰ事業所税とは 事業所税は、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資...
詳しく見る
-
会社設立
法人成りのメリット・デメリット
Ⅰ 法人成りのメリット ・社会的信用が高まり、新たな取引先の広がりや売上の増加が見込まれる・収入を個人(個人事業者)のみ...
詳しく見る
-
会社設立
法人成りとは
事業を個人事業者として営んでいた方が、新たに法人(会社)を設立し、その法人で事業を行うことを、一般に法人成り(法人化)と言いま...
詳しく見る
-
会社設立
創業融資サポート
Ⅰ 日本政策金融公庫「新創業融資」のサポートを行っています。 ・日本政策金融公庫の都内支店には、NA税理士法人の担当者が...
詳しく見る
-
会社設立
会社設立の流れ
Ⅰ 会社設立の流れ 必要事項の決定~登記申請まで、NA税理士法人及び提携の司法書士がサポートします。 1)必要事項...
詳しく見る
-
会社設立
会社設立サポート・無料相談
Ⅰ 当法人では、会社設立時にお客様にご準備いただくのは、下記2点のみです。 1.「株主」、「取締役」になる方の「印鑑登録...
詳しく見る
-
会社設立
会社設立FAQ
Q1 申込から設立(登記申請)までの期間は? A1 10日前後です。 Q2 会社設立に必要な費用は? ...
詳しく見る
-
消費税
消費税の納税義務者
商品の販売やサービスの提供、資産の貸付等を行った場合は、その取引に対して消費税が課税されます。消費税を納める義務がある者(納税...
詳しく見る
-
消費税
消費税の特例措置
Ⅰ 小規模事業者の納税義務の免除 事業者について、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者について...
詳しく見る
-
消費税
消費税の確定申告の基礎知識
Ⅰ 消費税とは 消費税とは、モノ・サービスの消費をしたときに課される税金で、ほぼ全ての国内における商品や製品の販売、サー...
詳しく見る
-
消費税
消費税FAQ
Q1 新しく事業を始めた場合には、いつから消費税を納めるのですか? A1 資本金が1,000万円未満の法人及び個人事...
詳しく見る
-
消費税
インボイス制度について
Ⅰ インボイス制度とは 消費税が10%へ引き上げられたことに伴い、2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。...
詳しく見る
-
助成金・補助金
補助金について
補助金について 経済産業省が管轄する補助金は、国の政策目標を達成するのに相応しい企業の取り組みに対して支給されるもので、...
詳しく見る
-
助成金・補助金
助成金について
Ⅰ助成金について 厚生労働省が提供する助成金には、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上など...
詳しく見る
-
助成金・補助金
助成金と補助金の違いとは
Ⅰ助成金と補助金の違いとは 助成金と補助金は、元々、その言葉そのものに大きな違いがあるわけではありません。他にも、給付金...
詳しく見る
-
建設業許可
建設業許可の要件
1.主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、または建設業に関する「経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)」...
詳しく見る
-
建設業許可
建設業許可とは
Ⅰ 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交...
詳しく見る
-
建設業許可
建設業許可FAQ
Q1 都知事許可を取得している個人事業主ですが、法人化することになった場合、許可を引き継ぐことはできますか。 A1 ...
詳しく見る
-
建設業許可
決算報告
建設業許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報告(事業年度終了報告書という行政庁もあります)を所定の様式で許...
詳しく見る
-
建設業許可
許可業種の追加
新たに許可の業種を追加する場合は、業種の追加申請をする必要があります。追加申請は新規許可に準じた方法で申請することになります。...
詳しく見る
-
決算
締め後分とは
Ⅰ 締め後分とは 締め後分とは、売上を例にとると、前月16日~当月15日までの売上に対して毎月請求書を発行している場合(...
詳しく見る
-
決算
決算の流れ
Ⅰ 中小企業が決算において税務申告書を作成するまでの手順を説明します。 1.月次処理の漏れ確認 経費精算の漏れや納品、仕...
詳しく見る
-
決算
決算の基礎知識
Ⅰ 会計期間 会社の営業年度で個人事業の場合は、その年の1月1日から12月31日の期間、法人の場合は、定款により任意の日...
詳しく見る
-
決算
決算とは
Ⅰ 決算とは 決算とは、会社や個人事業者の事業活動を会計期間(通常半年や一年)で区切り経営成績(もうけ具合)、企業の財政...
詳しく見る
-
決算
決算FAQ
Q1 貸借対照表とは? A1 貸借対照表とは、企業の一定時点における資産、負債、純資産の状態を表すために作成されるも...
詳しく見る
-
給与計算
当法人のサポート体制
Ⅰ 給与計算業務は、会社様ごとに様々な形があると思います。 勤怠の記録の取り方や給与明細の形式といったハード面も様々です...
詳しく見る
-
給与計算
給与計算の流れ
給与計算の流れ 1.勤怠データの確認出勤日数、勤務時間、残業時間、有給休暇など、支給額計算のベースとなる情報について、タ...
詳しく見る
-
給与計算
給与の仕組み(控除額など)
Ⅰ 給与の仕組みについて 給与計算は大きく3つに分かれています。(1)総支給額(額面金額)の計算、(2)控除額の計算、最...
詳しく見る
-
記帳代行
記帳代行FAQ
Q1 記帳代行とは? A1 記帳代行とは、法人様や個人事業主様に代わり、領収書の計算等の経理業務を行うサービスのこと...
詳しく見る
-
記帳代行
記帳代行 当法人の3つの特徴
Ⅰ 専任担当者制 専任担当者が、毎月の記帳代行から決算まで、責任を持って担当しております。 Ⅱ 手間がかからず簡単...
詳しく見る
-
マイナンバー
サポート体制
弊社では、下記のサポート体制でお客様の情報をお預かりしております。 1.指紋認証システムで入退室を管理職員以外の執務スペ...
詳しく見る
-
マイナンバー
マイナンバーとは
マイナンバーとは マイナンバー(個人番号)制度とは、行政を効率化し国民の利便性を高め、公正かつ公平な社会を実現する社会基...
詳しく見る
-
マイナンバー
マイナンバーFAQ
Q1 マイナンバーとマイナンバーカードの違いは何ですか? A1 マイナンバーとは、個人の識別番号として市区町村から住...
詳しく見る
-
マイナンバー
マイナンバーの取扱い
Ⅰ事業者がマイナンバーを取扱う際の注意すべき4つのポイント 1.マイナンバー取得についての注意点 (1)利用範囲と...
詳しく見る
-
確定申告
申告方法と期限
Ⅰ 必要書類を準備 所得の種類や控除の内容によっては、必要書類が異なりますが、日頃から領収書や証明書類などを整理しておく...
詳しく見る
-
譲渡所得
譲渡所得とは
Ⅰ 譲渡所得とは 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことです。 Ⅱ 譲渡所...
詳しく見る
-
譲渡所得
居住用財産譲渡時の軽減税率
Ⅰ 概要 居住用財産を売却して、一定の要件に該当するときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税...
詳しく見る
-
譲渡所得
居住用財産譲渡時の3,000万円控除
Ⅰ 概要 居住用財産を売却した際、譲渡所得から最高で3,000万円まで控除ができる特例があります。なお、当該特例を適用す...
詳しく見る
-
譲渡所得
贈与税FAQ
Q1 私たち夫婦(婚姻期間21年)は、分譲マンションの購入を検討しています。購入にあたり、妻に購入資金の一部を贈与し、2人の名...
詳しく見る
-
所得金額
所得金額の計算方式
Ⅰ 所得金額とは、収入金額から経費金額を差し引いた金額です。所得の種類ごとに、計算方式が異なります。 1.所得金額の計算...
詳しく見る
-
住民税
住民税とは
1.その年の1月1日の住所地の市区町村に収める税金。 2.前年の所得をもとに計算されます。 3.申告の方法 (1...
詳しく見る
-
事業所得
事業専従者青色申告控除とは
Ⅰ 青色事業専従者給与または事業専従者控除 個人事業主が生計を一にする親族に給料を支払った場合には、原則としてその給料は...
詳しく見る
-
事業所得
事業所得とは
事業所得とは、農業、漁業、製造業、棚卸業、小売業、サービス業その他対価を得て継続的に行う事業から生じる所得をいい、不動産の貸付...
詳しく見る
-
外国に財産がある方
居住者から非居住者になる方 注意点
Ⅰ 概要 居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人であり、原則、国内外を問わず、そ...
詳しく見る
-
外国に財産がある方
外国に財産をお持ちの方 税額計算 注意点
Ⅰ 原則 居住者は、原則として国内で生じた所得および国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。...
詳しく見る
-
外国に財産がある方
外国に財産をお持ちの方 注意点
Ⅰ 概要 近年、外国に財産をお持ちの方が増え、それに比例するように申告漏れや所得隠しが増加し、大きな社会問題となっていま...
詳しく見る
-
控除一覧
扶養控除とは
Ⅰ その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件の全てに当...
詳しく見る
-
控除一覧
配当控除とは
剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。...
詳しく見る
-
控除一覧
配偶者特別控除とは
年間の合計所得が48万円を超えるため配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得に応じて一定の金額の控除が受けられる場合があ...
詳しく見る
-
控除一覧
配偶者控除とは
Ⅰ 配偶者:民法上の規定による配偶者のこと(内縁関係は該当しない)が要件その他に1から3までの条件を満たしていないと控除の対象...
詳しく見る
-
控除一覧
政党等寄附金特別控除とは
政党等寄付金特別控除とは、個人が平成7年1月1日から令和6年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関...
詳しく見る
-
控除一覧
障害者控除とは
Ⅰ 次のいずれかに当てはまる人です。 1.常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人この人は、特別障害者...
詳しく見る
-
控除一覧
国外居住の扶養家族のいる方
Ⅰ 日本に居住し就労している外国人が扶養控除を受けられる制度があります。 税法上の扶養控除海外に住んでいる親族も日本国内...
詳しく見る
-
控除一覧
勤労学生控除とは
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。 1.対象と...
詳しく見る
-
控除一覧
寄附金控除とは
寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に所得控除を受けることができ...
詳しく見る
-
控除一覧
基礎控除とは
ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律納税者に適用されます。基礎控除の金額は、下記の...
詳しく見る
-
控除一覧
寡婦控除とは
寡婦とは、原則としてその年の12月31日時点でひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる方。 1.夫と離婚した後、婚姻...
詳しく見る
-
控除一覧
ひとり親控除とは
ひとり親とは、その年の12月31日時点で、未婚又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の3つの要件にすべて当てはまる人です。...
詳しく見る
-
控除一覧
損害保険料控除とは
Ⅰ 損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く) Ⅱ 損害保険料控除額の...
詳しく見る
-
控除一覧
生命保険料控除とは
Ⅰ あなたが生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合(※1)には、一定の金額の所得控除を受けることができます...
詳しく見る
-
控除一覧
小規模企業共済とは
Ⅰ あなたが次の掛金を支払った場合の控除 1.小規模企業共済法に規定された共済契約の掛金(旧第二種共済契約を除く)&nb...
詳しく見る
-
控除一覧
住宅耐震改修特別控除とは
Ⅰ 住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは 1.住宅耐震改修特別控除とは?居住者が令和5年12月31日までの間...
詳しく見る
-
控除一覧
住宅借入金等特別控除(ローン控除)
Ⅰ 住宅借入金等特別控除とは 1.住宅ローン控除とは住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)は、住宅を金融機関などからの借入...
詳しく見る
-
控除一覧
社会保険料控除とは
Ⅰ社会保険料控除とは あなたや生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額...
詳しく見る
-
控除一覧
雑損控除とは
Ⅰ 雑損控除とは 1.次のいずれかに該当する場合の控除 (1)あなたや、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元...
詳しく見る
-
控除一覧
誤りやすい医療費控除とは
Ⅰ 誤りやすい医療費控除とは 1.生計を一にしていない親の入院費を子が負担、その子が医療費控除している。 これは、...
詳しく見る
-
控除一覧
医療費控除の対象になる介護費用とは
Ⅰ医療費控除の対象になる介護費用とは 医師の証明、指定された施設、サービスの内容、要介護者である等、項目により様々な制限...
詳しく見る
-
控除一覧
医療費控除とは
Ⅰ 医療費控除とは あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のためにその年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の...
詳しく見る
-
控除一覧
所得から差し引かれる金額
Ⅰ 所得から差し引かれる金額とは 1.所得控除 所得控除とは、課税標準となる所得金額から一定金額を控除するものです...
詳しく見る
-
個人事業税
個人事業税の非課税事業と計算
Ⅰ 個人事業税の納税義務者とは 個人事業税の納税義務者とは、都道府県において第1種事業、第2種事業及び第3種事業を行う個...
詳しく見る
-
個人事業税
都税事務所からのお尋ね
Ⅰ都税事務所からのお尋ねについて 税務署で初めて確定申告をすると、「個人の事業内容に関する回答書」というお尋ねが届くこと...
詳しく見る
-
個人事業税
個人事業税とは
Ⅰ 個人事業税とは 個人事業税とは、個人の方が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対して係る税金(地...
詳しく見る
-
個人事業税
個人事業税FAQ
Q1 事務所又は事業所とは具体的にどういったものですか? A1 事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するもので...
詳しく見る
-
確定申告
個人が納める税金の種類
1. 所得税及び復興特別所得税 2. 消費税 3. 住民税 4. 個人事業税 5. 事業所税 6. 固定資産税 ...
詳しく見る
-
確定申告
決算書の内容
Ⅰ 青色申告者は、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかに該当する所得が生じた場合、確定申告書と合わせて決算書を提出する必要...
詳しく見る
-
確定申告
還付金とは
Ⅰ 還付金の税務上の取扱い 1.税金の課税の対象にはなりません。 2.ただし、還付金と共に還付加算金が交付された場...
詳しく見る
-
確定申告
確定申告の基礎知識
Ⅰ 確定申告とは 個人の確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入金額と経費金額より所得金額を算定し、そこ...
詳しく見る
-
確定申告
確定申告と年末調整の違いとは
Ⅰ 確定申告と年末調整の違いとは 1. 確定申告も年末調整も毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と...
詳しく見る
-
外国居住の日本人
非居住者の申告
外国に居住されている日本人は、その居住期間(または居住予定期間)が1年以上であれば、日本の所得税法上の「非居住者」に該当します...
詳しく見る
-
外国居住の日本人
非居住者の手続
日本の確定申告が必要となる人は、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果た...
詳しく見る
-
確定申告
103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁
Ⅰ これらの「壁」は、所得税あるいは社会保険料の負担が、ご本人に対して発生するかどうかを考える際、その境の目安となっている金額...
詳しく見る
-
M&A
M&Aとは
Ⅰ M&Aとは 企業の合併買収で、グローバル企業の買収以外にも中小企業でも事業承継問題で活用されています。 Ⅱ M...
詳しく見る
-
株式評価
株価評価とは
Ⅰ 取引相場のある上場株式は、取引所の株価をもって株価を評価します。 上場株式以外の株価(以下非上場株式等という)を評価...
詳しく見る
-
成年後見制度
成年後見制度
Ⅰ 成年後見制度とは、病気等により、判断能力が十分でなく、自分自身の権利を守ることができない成人の財産管理などを支援する制度で...
詳しく見る
-
信託
信託とは
Ⅰ 信託とは、委託者が自己の財産を受託者に対して受益者のために運用、管理を任せる制度です。 信託を活用した相続対策などに...
詳しく見る
-
相続関係資料
財産分割相談
Ⅰ 相続のご相談を受ける際には、相続人様の確認や相続財産の状況についてお尋ねいたします。それと同時に、分割状況も確認いたしてお...
詳しく見る
-
相続関係資料
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人がその取得する遺産について、その分割について話し合って合意した内容を記した書類です。書式は特に定まっ...
詳しく見る
-
相続関係資料
名義変更
Ⅰ 相続における名義変更とは 相続により取得した財産には、その名義変更が必要となるものがあります。 Ⅱ 不動産の名...
詳しく見る
-
相続関係資料
相続に関わる手続き
Ⅰ 相続には、不動産や預貯金、その他の動産などの様々な名義変更等、下記のような手続きが必要になります。 1.名義変更 ...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税FAQ
Q1 贈与税には110万円の基礎控除があると聞きましたが、1回の贈与につき、1年間で誰かひとりに対して110万円までなら贈与税...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税がかかる財産・かからない財産
Ⅰ 贈与税の課税価格 贈与税のかかる財産は、相続税がかかる財産とほぼ変わりません。 1.本来の贈与財産 ◆...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税の申告・納税
Ⅰ 贈与税の申告 原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに、もらった人の住所を所轄する税...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税の計算
Ⅰ 贈与税の計算及び申告 1.贈与税計算の流れ贈与税は、財産をもらった人が、その年の1月1日から12月31日までに贈与を...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与・贈与税とは
Ⅰ 贈与とは 贈与は、ある人が「あげますよ」という意思をもって、無償で自分の財産をあげることです。また、もらう側も「もら...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非...
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは、結婚・子育て資金という使途は限られますが、贈与税の非課税範...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは、教育資金という使途は限られますが、贈与者が亡くなった後も要件を満た...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税
直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度とは、住宅取得資金という使途は限られていますが、贈与税非課税で直系卑属...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除
夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するため...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税額の計算
Ⅰ 贈与税額の計算 1.相続時精算課税に係る贈与者からの贈与の場合まずは、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与...
詳しく見る
-
生前贈与による相続税対策贈与・贈与税
生前贈与による相続税対策
相続時精算課税制度が改正され、2024年1月から適用されることとなります。 これまでは活用の機会が限られていた相続時精算課税制...
詳しく見る
-
相続が発生した方
相続が発生した方(生前贈与)
相続の開始前3年以内に被相続人から財産を贈与によって取得した人は、その贈与財産の価額を相続税の課税財産に加算したうえで相続税の...
詳しく見る
-
相続が発生した方
相続が発生した方(受け取る側)
Ⅰ 遺産分割 相続税を申告・納付するにあたっては、まずは遺産を分ける手続き、いわゆる遺産分割が必要です。ご家族が亡くなっ...
詳しく見る
-
準確定申告
準確定申告とは
Ⅰ 準確定申告とは 少し聞きなれない言葉ではありますが、年の中途で死亡した人は、3月15日が提出期限の確定申告書ではなく...
詳しく見る
-
相続税
相続税FAQ
Q1 相続税には基礎控除があると聞きましたが、どのくらいの金額になるのでしょうか? A1 相続税には、法定相続人の数...
詳しく見る
-
相続税
名義財産とは
Ⅰ 名義財産 名義が親族の名義になっていて、被相続人の名義になっていなくても、実質的に所有者が被相続人であればその財産は...
詳しく見る
-
相続税
相続税の申告と流れ
Ⅰ 相続税の申告 相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した者が申告と納付をすることになります。相続の開始を知った日(亡...
詳しく見る
-
相続税
サポート体制
1.相続無料相談相続に関するあらゆるご相談をお受け致します。初回一時間無料です。 2.パートナー提携体制各種専門家(弁...
詳しく見る
-
遺言
遺言の意味
Ⅰ 遺言とは 遺言とは、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺...
詳しく見る
-
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは
Ⅰ 軽減の内容 相続等で財産を取得した配偶者は、相続税が軽減されます。 1億6000万円までか、法定相続分ま...
詳しく見る
-
小規模宅地等の特例
相続する宅地で、被相続人が住んでいた土地などには評価額...
Ⅰ 居住用宅地の減額 被相続人の居住の用に供されていた宅地を、一定の者が相続する場合、その宅地の評価額は80%減額され...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
相続・贈与・相続税の違いとは
相続とは、個人の死亡により開始し、財産と債務の両方が移転します。手続きなしに、全財産が自動的に相続人に受け継がれます。贈与と...
詳しく見る
-
相続関係資料
相続関係資料の作成
相続税の申告においては、戸籍、土地・建物の登記簿謄本等様々な書類を取得する必要性に加え、作成しなければならない書類が多数ありま...
詳しく見る
-
相続税 かかる財産・かからない財産
相続税のかかる財産・かからない財産
Ⅰ 相続税のかからない財産とは 1.墓地、墓石、仏壇など 墓地、墓石や仏壇などは、価値判断が難しい部分もあり...
詳しく見る
-
相続税の計算
相続税の計算には、大きく分けると、三段階があります。
Ⅰ 課税価格の計算方法 相続や遺贈により財産を取得した人の各々の財産の総額を個別に計算します。 相続又遺贈により...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
8月の税務労務スケジュール
8月の主な税務・労務スケジュール 本記事では、8月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。税務...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
7月の税務労務スケジュール
7月の主な税務・労務スケジュール 本記事では、7月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。税務...
詳しく見る
-
社会保険
算定基礎届・年度更新について
Ⅰ 社会保険の算定基礎届とは 健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
6月の税務労務スケジュール
6月の主な税務・労務スケジュール 本記事では、6月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。税務...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
【103万円の壁】の現在地
Ⅰ はじめに 令和7年度改正による「所得税」の「控除」に関する主な変更点は、 令和7年2月4日に国会に提出された...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
5月の税務労務スケジュール
5月の主な税務・労務スケジュール 本記事では、5月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。税務...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
税効果会計
Ⅰ 税効果会計とは 企業会計と税務会計は、計算目的の違いから一時的なズレ(タイミングの違い)が生じます。税効果会計とは、...
詳しく見る
-
事業承継
【親族内承継】とは
Ⅰ 【親族内承継】とは 親族内承継とは、現経営者の子供や孫、兄弟など親族に会社を引き継ぐ承継方法です。 第三者へ...
詳しく見る
-
競馬と確定申告
Ⅰ はじめに 競馬を楽しんでいますか。日本において、競馬は違法ではありません。しかし、ギャンブルという側面からどうしても...
詳しく見る
-
確定申告
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて
1.概要 国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、...
詳しく見る
-
福利厚生費
iDeCo+(イデコプラス)とは
個人の年金制度として人気の高いiDeCo(個人型確定拠出年金)ですが、従業員加入のiDeCoに、企業側が上乗せ拠出できる制度が...
詳しく見る
-
会社設立
非営利型一般社団法人による診療所設立のメリット
医業を行う個人事業主が法人化する場合、一般的には医療法人を設立することが多いですが、近年は一般社団法人がクリニックを開...
詳しく見る
-
事業承継
事業承継とは
はじめに 事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。具体的には経営権のほか、株式等の会社の資産や事業に関...
詳しく見る
-
確定申告
財産債務調書の提出義務
Ⅰ 財産債務調書とは 一定の所得金額および財産価額に達している人が、確定申告書とは別に提出しなければならない法...
詳しく見る
-
口座凍結について
「口座凍結」という言葉は...
詳しく見る
-
事業承継
事業承継税制と相続時精算課税制度の併用適用
はじめに 従来、事業承継税制と相続時精算課税制度は併用適用することが出来ませんでしたが、平成29年度税制改正によりその併...
詳しく見る
-
社会保険
「マイナ保険証」活用してますか?
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が廃止となり、保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)に引き継がれま...
詳しく見る
-
確定申告
暗号資産(仮想通貨)にかかる税金と確定申告について
はじめに ビットコイン(BTC)などの暗号資産(仮想通貨)は、投資対象として多くの関心を集めています。「投資で利益を得た...
詳しく見る
-
確定申告
外貨取引における為替差損益
最近の為替相場は、さまざまな要因によって影響を受け不安定な状況が続いていますが、円預金より高い金利が得られる外貨預金で将来のた...
詳しく見る
-
消費税
2割特例の適用範囲
Ⅰインボイス制度のおさらい インボイス制度は、消費税の標準税率10%と軽減税率8%が混在する複数税率制度のもと、売手側と...
詳しく見る
-
相続税
今すぐできる相続対策とは?
Ⅰ 2024年の税制改正による影響 2024年の税制改正では相続税・贈与税関連の法律が大幅に変わりました。詳細はこちらに...
詳しく見る
-
人事採用給与計算
労働条件の明示事項
Ⅰはじめに 2024年4月1日より法改正に伴い労働条件の明示事...
詳しく見る
-
消費税の確定申告
外国法人の消費税の納税義務
はじめに 外国法人が日本国内で法人税の課税の対象となる取引を行えば、当然法人税が課税されることとなりますが、たと...
詳しく見る
-
7月の税務スケジュール
色とりどりの紫陽花に、梅雨の訪れを感じる季節となりました。7月の主な「税務・申告に関するスケジュール」を掲載しております。税務...
詳しく見る
-
NA税理士法人の一日
はじめに 税理士法人は多くの人々にとって謎めいた場所です。 そこで、今回はNA税理士法人の一日を覗いてみましょ...
詳しく見る
-
遺言
ペットに相続は出来るか
Ⅰ ペットへの相続 飼い主にもしものことがあった際、ペットに財産を相続させることはできるのでしょうか。ペットの法的解釈と...
詳しく見る
-
相続が発生した方
相続登記の申請義務化
2024年4月1日より、不動産所有権に関する相続登記の申請義務化が始まりました。すでに多くの媒体で取り上げられているため、目に...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
地価公示価格
Ⅰ はじめに 3月末に令和6年度の地価公示価格が発表されました。令和6年は3年に一度の固定資産評価額の評価替えの年でもあ...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
令和6年分所得税・住民税の定額減税
定額減税について、 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。 今後、税制改正法案が成立し...
詳しく見る
-
確定申告
確定申告が始まっています。
はじめに 確定申告書の受付が始まっています。 令和5年(2023年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は...
詳しく見る
-
確定申告
令和5年分確定申告の効率化
Ⅰ 令和5年分確定申告でリリースされるe-Taxの新機能 令和5年分確定申告より、確定申告書等作成コーナーで下記1.のサ...
詳しく見る
-
社会保険
退職代行サービスについて知っておきたいこと
Ⅰ はじめに 自己都合退職の法的なルール 近年、従業員の代わりに退職連絡を請け負う「退職代行サービス」が増えています...
詳しく見る
-
社会保険給与計算
社会保険の年収の壁について
配偶者の扶養内で働いているパート従業員が就業調整を意識する「年収の壁」について、 2023年10月に「年収の壁・支援強化パッケ...
詳しく見る
-
会社設立
医療法人とは
個人事業主の方であれば法人化を検討される方も多くいらっしゃると思いますが、事業内容が「医業」である場合、つまり、ドクタ...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
令和6年1月からの電子取引データ保存
今年10月からインボイス制度が始まり、現場は日々対応に追われ混乱しています。 そんな中、来年1月からは電子帳簿保...
詳しく見る
-
年末調整
年末調整手続きの電子化
今年も年末調整の時期になりました。 まだ紙で従業員から申告書を提出してもらっている事業所が多いのではないでしょうか。 各種申告...
詳しく見る
-
人事採用
人手不足時代の採用戦略
はじめに 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)の減少が続く中、人手不足が経営と直結する状況になりつつあります。中小企業に...
詳しく見る
-
消費税
電子インボイスによる経理業務の効率化
Ⅰ 概要 10月1日から、インボイス制度が始まりました。制度開始に伴い、記帳業務が煩雑になるため、今後記帳に要する手間や...
詳しく見る
-
給与計算
令和5年度の地域別最低賃金
今年度の都道府県ごとの最低賃金が決定され、全国平均額は1,004円となり初めて1,000円を超えました。 東京都については20...
詳しく見る
-
退職金
退職金の法的性格(裁判事例を鑑みて)
飲酒運転により懲戒免職となった教員に対する退職金を巡る訴訟において、最高裁は退職金の支給を認めないとする判決を下した。 長年勤...
詳しく見る
-
社会保険
育児・介護休業法の改正
はじめに・・・ 少子化の進行は、人口の減少と高齢化を通じて社会経済に多大な影響を及ぼします。 2022年には合計特...
詳しく見る
-
消費税
適格請求書発行事業者になるかならないかの選択
2023年10月から開始されるインボイス制度に向け、仕入税額控除を受けるためには登録申請手続きを行う必要がありますが、比較的小...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
修正申告・更正の請求
修正申告・更正の請求は法定申告期限後に、計算違いなど申告内容の間違いに気が付いたときに行う手続きです。 Ⅰ修正申告とは ...
詳しく見る
-
令和5年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内
令和5年4月に、厚生労働省から「令和5年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内」が公開されました。 簡略版と詳細版があり...
詳しく見る
-
個人 融資
クラウドローンのご紹介
弊所はクラウドローン株式会社様と業務提携を致しました。 クラウドローンとは、利用者が希望する融資に合わせて、...
詳しく見る
-
年末調整
源泉徴収制度について
Ⅰ 源泉徴収制度の意義 所得税は、納税者自身がその年の所得金額と税額を計算の上、自主的に申告して納付する「申告納税制度」...
詳しく見る
-
消費税
リバースチャージ
Ⅰ リバースチャージとは 消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行...
詳しく見る
-
会社設立
法人名義の銀行口座
登記も完了し、「さぁこれから事業を始めよう」と思われている起業家の皆さんも多いと思いますが、 会社設立後に振込等の資金移動のた...
詳しく見る
-
社会保険
労働保険料の納付
Ⅰ 労働保険とは 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。 加入などの各種手続きを労災保険は労...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
増資・減資とは
Ⅰ 増資とは 増資とは、資金調達のために新株を発行するなどして資本金を増やすことをいいます。 増資によるメリットは...
詳しく見る
-
相続税の計算
相続税の時価と財産評価
相続人が被相続人から相続や遺贈で受け取った財産には相続税が課税されます。財産は時価に基づいて評価されるということが相続...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
みなし贈与にご注意!
Ⅰ.はじめに 個人から年間110万を超える財産の受取があった場合、受け取った側の個人が、の3月15日までに申告・納税...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
バーチャルオフィスとは
Ⅰ バーチャルオフィスとは バーチャルオフィスとは事務所用の住所を貸し出すサービスです。 住所の貸し出しだけ行って...
詳しく見る
-
譲渡所得
租税特別措置法第 40 条の規定による承認申請書
個人が寄付金を支出した場合には、寄付金控除の適用があります。しかし、土地、建物などの財産を法人に寄付した場合には・・・ ...
詳しく見る
-
確定申告
副業収入がある方の確定申告について
Ⅰ 副業と現代について サラリーマンは通常、会社が行う年末調整のみでその年分の所得税の精算が完了するため、一定の場合を除...
詳しく見る
-
給与計算
給与のデジタル払い
買い物などで現金の代わりにスマホを使って支払いを済ませる「キャッシュレス決済」が急速に普及しています。 このキャッシュレ...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
数値で把握できる経営指標
経営指標とは会社の経営状態を数字であらわした指標のことです。融資の際の判断材料として使用されたり、自社を分析して経営課題や目標...
詳しく見る
-
相続が発生した方
配偶者居住権のメリット・デメリット
長年連れ添った配偶者を亡くすということは大きな悲しみを伴うものです。そのような中、残された配偶者が住みなれた家を出ていかなけれ...
詳しく見る
-
確定申告
医師・歯科医師の概算経費特例
医師又は歯科医師は、社会保険診療報酬が年5,000万円以下の年分について、「概算経費率」による所得計算を行うことができます。概...
詳しく見る
-
税務・会計用語集記帳代行
税理士に税務代行してもらうことのメリットとデメリット
事業を始めようと思った時に何から始めればよいのか、その相談先としてまず税理士に相談すれば良いという情報を得て、弊社にご面談に来...
詳しく見る
-
控除一覧
ふるさと納税 とは
最近では身近な人もふるさと納税をされる方が増えてきています。魅力的な返礼品も増えて、今年からふるさと納税を始めてみよう、とお考...
詳しく見る
-
消費税
棚卸資産に係る消費税額の調整
棚卸資産に係る消費税額の調整 Ⅰ 免税事業者が課税事業者となった場合 課税事業者となる日の前日において所有する棚卸...
詳しく見る
-
年末調整
令和4年分 年末調整について
Ⅰ 令和4年分 年末調整の変更点 そろそろ、令和4年分の年末調整の準備・スケジュールを考え始めている方もいらっしゃるので...
詳しく見る
-
社会保険
社会保険の適用拡大
2022年10月より、パート・アルバイトの方についての社会保険の適用が拡大されます。 社会保険は、原則としては週の労働時...
詳しく見る
-
消費税
インボイス制度Q&Aのご案内
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
欠損金の繰戻し還付とは
Ⅰ法人税法上の概要 この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額をその事...
詳しく見る
-
税務・会計用語集
クラウド会計ソフトの概要
Ⅰ クラウド会計ソフトとは 会計ソフトとは、簿記のルールに基づいて会社で行われる取引の一つ一つを記録し、貸借対照...
詳しく見る
-
消費税
計算方法・課税期間・申告時期
Ⅰ 計算方法 消費税は、事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて「納付する消費税」を計算し納付します...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
法人税の確定申告の基礎知識
Ⅰ 法人税の確定申告の申告期限 1.原則は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。 2.災害があった場合や、会計...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
法人税の確定申告FAQ
Q1 法人税の計算は、決算書の利益に税率を掛けるんでしょうか? A1 いいえ。法人税の所得の金額に税率を掛けます。1.法...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
税務上の繰延資産とは
Ⅰ 税務上の繰延資産とは 法人が支出する費用で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものを、繰延資産と言います。さ...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
青色申告とは
Ⅰ 青色申告とは 青色申告とは、一定の要件を満たすことにより、青色申告書を用いて申告する手続きです。もともとが青色の申告...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
青色欠損金とは
Ⅰ 青色欠損金とは 青色欠損金とは、簡単に言ってしまえば、決算時に生じた赤字のことです。税法上この赤字を「欠損金」といい...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
賃上げ促進税制とは
Ⅰ 賃上げ促進税制とは 賃上げや人材育成への投資を積極的に行う法人が、雇用者に支払う給与等の支給額を一定割合以上増加させ...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
交際費とは
Ⅰ 交際費とは 交際費等とは、「交際費、接待費、その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
固定資産の特別償却・控除
Ⅰ 固定資産の特別償却とは 1. 特別な規定により、通常の減価償却を超えて償却費を計上すること 2. 規定の種類に...
詳しく見る
-
法人税の確定申告
減価償却費とは
Ⅰ 減価償却費とは 事業などの業務のために用いられる資産(建物、建物付属設備、車両運搬具など)を取得した際は、その取得に...
詳しく見る
-
法人住民税
法人税割とは
法人税割は、法人税額を基として税率を乗じて法人住民税(法人税割)を計算します。 法人税額 × 法人住民税の税率 = 法人...
詳しく見る
-
法人住民税
法人住民税とは
1.申告納税先 法人に対しても、道府県民税と市区町村民税、すなわち住民税が課税され、これを一般には法人住民税といいます。...
詳しく見る
-
法人住民税
法人均等割とは
Ⅰ 均等割とは 1.法人均等割とは 市町村民税は、資本金等の金額と従業員数に応じて、都道府県民税は資本金等の金額に...
詳しく見る
-
法人事業税
法人事業税の非課税事業とは
Ⅰ 法人事業税の非課税事業とは 法人事業税の納税義務者は、原則として事業を行うすべての法人(公益法人等は、収益事業を行...
詳しく見る
-
法人事業税
法人事業税の税率表
下記URL(東京都主税局HP)をご確認ください。 URL:https://www.tax.metro.tokyo.lg....
詳しく見る
-
法人事業税
法人事業税の課税方式の見直しについて
これまで、電気供給業に係る法人事業税は「収入割」のみ適用されていましたが、令和2年度税制改正により、電気供給業のうち発電・小売...
詳しく見る
-
法人事業税
法人事業税とは
Ⅰ 地方税申告書とは 地方税申告書はどのようなものか。会社の利益(所得)に対しては、法人税の他に地方税が課されます。地方...
詳しく見る
-
法人事業税
分割法人の取り扱い
Ⅰ 分割基準とは 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人又は個人に対しては、その法人又は個人...
詳しく見る
-
法人事業税
所得割
Ⅰ 所得割とは 所得割とは、所得金額に対して事業税率を乗じて計算します。この場合の所得金額は、法人税別表4で算出される所...
詳しく見る
-
法人事業税
収入割
Ⅰ 収入割とは 電気供給業・ガス供給業・保険業など、所得金額を課税標準にするのは妥当ではない法人に課されるものです。収入...
詳しく見る
-
法人事業税
外形標準課税
Ⅰ 外形標準課税とは 外形標準課税は、従来の所得に対する事業税が課される法人(特別法人等の一定の法人を除きます)に対して...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
自己資本と他人資本とは
Ⅰ 資本とは 資本とは事業活動の元手となるお金のことです。 Ⅱ 自己資本とは 自己資本とは資本のうち、資本金...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
人件費とは
Ⅰ 人件費とは 人件費とは、人事関連費用の総額です。具体的には、給与賃金手当、賞与、福利厚生費(法定福利費と法定外福利費...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
費用収益対応の原則とは
Ⅰ 費用収益対応の原則とは 費用、収益対応の原則とは、期間収益とそれに関連する期間費用を対応させて、期間損益を計算する原...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
引当金とは
引当金の設定要件は下記4つを満たすことが前提となります。 ◆将来の特定の費用又は損失◆その発生が当期以前の事象に起因する...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
未払金と未払費用とは
Ⅰ 未払費用とは 未払費用とは、一定の契約に従い、”継続して”役務の提供を受ける場合、既に提供さ...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
仕入債務とは
Ⅰ 仕入債務とは 仕入債務とは、商品や材料の仕入などを購入し、支払いをすぐに行わず、後で支払うことを約束した債務のことで...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
資産(資産の種類)とは
Ⅰ 棚卸資産とは 在庫の事です。在庫の種類も、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品などがあります。 棚卸資産の貸借対...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
注記表とは
Ⅰ 注記表とは 注記表とは、企業の貸借対照表や損益計算表の財務諸表についての情報の補足事項をまとめたものを指します。会社...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
株主資本等変動計算書とは
Ⅰ 株主資本等変動計算書とは 貸借対照表の純資産の変動状況を表す財務諸表のことです。主に、会社の利益を何に使ったのかを知...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
製造原価報告書とは
Ⅰ 製造原価報告書とは 製造業が当期間に製造した製品の製造原価を記入した計算書類のことで、財務書表の一つとして損益計算書...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
B/SとP/Lの違い
貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)は、企業の財務状況を報告するための2つの重要な書類です。両者の目的と提供する情報には...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
損益計算書とは
Ⅰ 損益計算書とは、一定期間における企業の経営成績をまとめた表のことです。 費用、収益、それらを差し引きして出る利益の3...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
貸借対照表とは
Ⅰ 貸借対照表とは、一定時期における企業の財政状態をまとめた表のことです。 資産、負債、純資産の3つの項目が表記されてお...
詳しく見る
-
簿記・会計関連
簿記・会計とは
Ⅰ 簿記とは 簿記とは主に複式簿記のことを指し、15世紀大航海時代のイタリアで複式簿記が出来上がったと言われています。貴...
詳しく見る
-
法人事業税
特別法人事業税とは
Ⅰ 特別法人事業税とは 令和元年度税制改正により、地方間の税収偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離し、国税である特...
詳しく見る
-
事業承継
事業承継の進め方
スムーズに事業承継を進めるためには、早期に準備に着手することが大切です。まずは、事業承継に向けた準備の必要性を認識してスタート...
詳しく見る
-
事業承継
事業承継で引き継ぐ対象
Ⅰ経営(人)の承継 事業承継における「経営の承継」とは「経営権」の承継をいいます。特に中小企業においては経営者個人にノウ...
詳しく見る
-
法人事業税
事業所税の仕組み
Ⅰ事業所税の仕組み 事業所等の床面積を対象とする資産割、従業者の給与総額を対象とする従業者割に分かれる。 1.事業...
詳しく見る
-
法人事業税
事業所税とは
Ⅰ事業所税とは 事業所税は、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資...
詳しく見る
-
会社設立
法人成りのメリット・デメリット
Ⅰ 法人成りのメリット ・社会的信用が高まり、新たな取引先の広がりや売上の増加が見込まれる・収入を個人(個人事業者)のみ...
詳しく見る
-
会社設立
法人成りとは
事業を個人事業者として営んでいた方が、新たに法人(会社)を設立し、その法人で事業を行うことを、一般に法人成り(法人化)と言いま...
詳しく見る
-
会社設立
創業融資サポート
Ⅰ 日本政策金融公庫「新創業融資」のサポートを行っています。 ・日本政策金融公庫の都内支店には、NA税理士法人の担当者が...
詳しく見る
-
会社設立
会社設立の流れ
Ⅰ 会社設立の流れ 必要事項の決定~登記申請まで、NA税理士法人及び提携の司法書士がサポートします。 1)必要事項...
詳しく見る
-
会社設立
会社設立サポート・無料相談
Ⅰ 当法人では、会社設立時にお客様にご準備いただくのは、下記2点のみです。 1.「株主」、「取締役」になる方の「印鑑登録...
詳しく見る
-
会社設立
会社設立FAQ
Q1 申込から設立(登記申請)までの期間は? A1 10日前後です。 Q2 会社設立に必要な費用は? ...
詳しく見る
-
消費税
消費税の納税義務者
商品の販売やサービスの提供、資産の貸付等を行った場合は、その取引に対して消費税が課税されます。消費税を納める義務がある者(納税...
詳しく見る
-
消費税
消費税の特例措置
Ⅰ 小規模事業者の納税義務の免除 事業者について、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者について...
詳しく見る
-
消費税
消費税の確定申告の基礎知識
Ⅰ 消費税とは 消費税とは、モノ・サービスの消費をしたときに課される税金で、ほぼ全ての国内における商品や製品の販売、サー...
詳しく見る
-
消費税
消費税FAQ
Q1 新しく事業を始めた場合には、いつから消費税を納めるのですか? A1 資本金が1,000万円未満の法人及び個人事...
詳しく見る
-
消費税
インボイス制度について
Ⅰ インボイス制度とは 消費税が10%へ引き上げられたことに伴い、2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。...
詳しく見る
-
助成金・補助金
補助金について
補助金について 経済産業省が管轄する補助金は、国の政策目標を達成するのに相応しい企業の取り組みに対して支給されるもので、...
詳しく見る
-
助成金・補助金
助成金について
Ⅰ助成金について 厚生労働省が提供する助成金には、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上など...
詳しく見る
-
助成金・補助金
助成金と補助金の違いとは
Ⅰ助成金と補助金の違いとは 助成金と補助金は、元々、その言葉そのものに大きな違いがあるわけではありません。他にも、給付金...
詳しく見る
-
建設業許可
建設業許可の要件
1.主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、または建設業に関する「経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)」...
詳しく見る
-
建設業許可
建設業許可とは
Ⅰ 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交...
詳しく見る
-
建設業許可
建設業許可FAQ
Q1 都知事許可を取得している個人事業主ですが、法人化することになった場合、許可を引き継ぐことはできますか。 A1 ...
詳しく見る
-
建設業許可
決算報告
建設業許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報告(事業年度終了報告書という行政庁もあります)を所定の様式で許...
詳しく見る
-
建設業許可
許可業種の追加
新たに許可の業種を追加する場合は、業種の追加申請をする必要があります。追加申請は新規許可に準じた方法で申請することになります。...
詳しく見る
-
決算
締め後分とは
Ⅰ 締め後分とは 締め後分とは、売上を例にとると、前月16日~当月15日までの売上に対して毎月請求書を発行している場合(...
詳しく見る
-
決算
決算の流れ
Ⅰ 中小企業が決算において税務申告書を作成するまでの手順を説明します。 1.月次処理の漏れ確認 経費精算の漏れや納品、仕...
詳しく見る
-
決算
決算の基礎知識
Ⅰ 会計期間 会社の営業年度で個人事業の場合は、その年の1月1日から12月31日の期間、法人の場合は、定款により任意の日...
詳しく見る
-
決算
決算とは
Ⅰ 決算とは 決算とは、会社や個人事業者の事業活動を会計期間(通常半年や一年)で区切り経営成績(もうけ具合)、企業の財政...
詳しく見る
-
決算
決算FAQ
Q1 貸借対照表とは? A1 貸借対照表とは、企業の一定時点における資産、負債、純資産の状態を表すために作成されるも...
詳しく見る
-
給与計算
当法人のサポート体制
Ⅰ 給与計算業務は、会社様ごとに様々な形があると思います。 勤怠の記録の取り方や給与明細の形式といったハード面も様々です...
詳しく見る
-
給与計算
給与計算の流れ
給与計算の流れ 1.勤怠データの確認出勤日数、勤務時間、残業時間、有給休暇など、支給額計算のベースとなる情報について、タ...
詳しく見る
-
給与計算
給与の仕組み(控除額など)
Ⅰ 給与の仕組みについて 給与計算は大きく3つに分かれています。(1)総支給額(額面金額)の計算、(2)控除額の計算、最...
詳しく見る
-
記帳代行
記帳代行FAQ
Q1 記帳代行とは? A1 記帳代行とは、法人様や個人事業主様に代わり、領収書の計算等の経理業務を行うサービスのこと...
詳しく見る
-
記帳代行
記帳代行 当法人の3つの特徴
Ⅰ 専任担当者制 専任担当者が、毎月の記帳代行から決算まで、責任を持って担当しております。 Ⅱ 手間がかからず簡単...
詳しく見る
-
マイナンバー
サポート体制
弊社では、下記のサポート体制でお客様の情報をお預かりしております。 1.指紋認証システムで入退室を管理職員以外の執務スペ...
詳しく見る
-
マイナンバー
マイナンバーとは
マイナンバーとは マイナンバー(個人番号)制度とは、行政を効率化し国民の利便性を高め、公正かつ公平な社会を実現する社会基...
詳しく見る
-
マイナンバー
マイナンバーFAQ
Q1 マイナンバーとマイナンバーカードの違いは何ですか? A1 マイナンバーとは、個人の識別番号として市区町村から住...
詳しく見る
-
マイナンバー
マイナンバーの取扱い
Ⅰ事業者がマイナンバーを取扱う際の注意すべき4つのポイント 1.マイナンバー取得についての注意点 (1)利用範囲と...
詳しく見る
-
確定申告
申告方法と期限
Ⅰ 必要書類を準備 所得の種類や控除の内容によっては、必要書類が異なりますが、日頃から領収書や証明書類などを整理しておく...
詳しく見る
-
譲渡所得
譲渡所得とは
Ⅰ 譲渡所得とは 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことです。 Ⅱ 譲渡所...
詳しく見る
-
譲渡所得
居住用財産譲渡時の軽減税率
Ⅰ 概要 居住用財産を売却して、一定の要件に該当するときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税...
詳しく見る
-
譲渡所得
居住用財産譲渡時の3,000万円控除
Ⅰ 概要 居住用財産を売却した際、譲渡所得から最高で3,000万円まで控除ができる特例があります。なお、当該特例を適用す...
詳しく見る
-
譲渡所得
贈与税FAQ
Q1 私たち夫婦(婚姻期間21年)は、分譲マンションの購入を検討しています。購入にあたり、妻に購入資金の一部を贈与し、2人の名...
詳しく見る
-
所得金額
所得金額の計算方式
Ⅰ 所得金額とは、収入金額から経費金額を差し引いた金額です。所得の種類ごとに、計算方式が異なります。 1.所得金額の計算...
詳しく見る
-
住民税
住民税とは
1.その年の1月1日の住所地の市区町村に収める税金。 2.前年の所得をもとに計算されます。 3.申告の方法 (1...
詳しく見る
-
事業所得
事業専従者青色申告控除とは
Ⅰ 青色事業専従者給与または事業専従者控除 個人事業主が生計を一にする親族に給料を支払った場合には、原則としてその給料は...
詳しく見る
-
事業所得
事業所得とは
事業所得とは、農業、漁業、製造業、棚卸業、小売業、サービス業その他対価を得て継続的に行う事業から生じる所得をいい、不動産の貸付...
詳しく見る
-
外国に財産がある方
居住者から非居住者になる方 注意点
Ⅰ 概要 居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人であり、原則、国内外を問わず、そ...
詳しく見る
-
外国に財産がある方
外国に財産をお持ちの方 税額計算 注意点
Ⅰ 原則 居住者は、原則として国内で生じた所得および国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。...
詳しく見る
-
外国に財産がある方
外国に財産をお持ちの方 注意点
Ⅰ 概要 近年、外国に財産をお持ちの方が増え、それに比例するように申告漏れや所得隠しが増加し、大きな社会問題となっていま...
詳しく見る
-
控除一覧
扶養控除とは
Ⅰ その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件の全てに当...
詳しく見る
-
控除一覧
配当控除とは
剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。...
詳しく見る
-
控除一覧
配偶者特別控除とは
年間の合計所得が48万円を超えるため配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得に応じて一定の金額の控除が受けられる場合があ...
詳しく見る
-
控除一覧
配偶者控除とは
Ⅰ 配偶者:民法上の規定による配偶者のこと(内縁関係は該当しない)が要件その他に1から3までの条件を満たしていないと控除の対象...
詳しく見る
-
控除一覧
政党等寄附金特別控除とは
政党等寄付金特別控除とは、個人が平成7年1月1日から令和6年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関...
詳しく見る
-
控除一覧
障害者控除とは
Ⅰ 次のいずれかに当てはまる人です。 1.常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人この人は、特別障害者...
詳しく見る
-
控除一覧
国外居住の扶養家族のいる方
Ⅰ 日本に居住し就労している外国人が扶養控除を受けられる制度があります。 税法上の扶養控除海外に住んでいる親族も日本国内...
詳しく見る
-
控除一覧
勤労学生控除とは
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。 1.対象と...
詳しく見る
-
控除一覧
寄附金控除とは
寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に所得控除を受けることができ...
詳しく見る
-
控除一覧
基礎控除とは
ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律納税者に適用されます。基礎控除の金額は、下記の...
詳しく見る
-
控除一覧
寡婦控除とは
寡婦とは、原則としてその年の12月31日時点でひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる方。 1.夫と離婚した後、婚姻...
詳しく見る
-
控除一覧
ひとり親控除とは
ひとり親とは、その年の12月31日時点で、未婚又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の3つの要件にすべて当てはまる人です。...
詳しく見る
-
控除一覧
損害保険料控除とは
Ⅰ 損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く) Ⅱ 損害保険料控除額の...
詳しく見る
-
控除一覧
生命保険料控除とは
Ⅰ あなたが生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合(※1)には、一定の金額の所得控除を受けることができます...
詳しく見る
-
控除一覧
小規模企業共済とは
Ⅰ あなたが次の掛金を支払った場合の控除 1.小規模企業共済法に規定された共済契約の掛金(旧第二種共済契約を除く)&nb...
詳しく見る
-
控除一覧
住宅耐震改修特別控除とは
Ⅰ 住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは 1.住宅耐震改修特別控除とは?居住者が令和5年12月31日までの間...
詳しく見る
-
控除一覧
住宅借入金等特別控除(ローン控除)
Ⅰ 住宅借入金等特別控除とは 1.住宅ローン控除とは住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)は、住宅を金融機関などからの借入...
詳しく見る
-
控除一覧
社会保険料控除とは
Ⅰ社会保険料控除とは あなたや生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額...
詳しく見る
-
控除一覧
雑損控除とは
Ⅰ 雑損控除とは 1.次のいずれかに該当する場合の控除 (1)あなたや、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元...
詳しく見る
-
控除一覧
誤りやすい医療費控除とは
Ⅰ 誤りやすい医療費控除とは 1.生計を一にしていない親の入院費を子が負担、その子が医療費控除している。 これは、...
詳しく見る
-
控除一覧
医療費控除の対象になる介護費用とは
Ⅰ医療費控除の対象になる介護費用とは 医師の証明、指定された施設、サービスの内容、要介護者である等、項目により様々な制限...
詳しく見る
-
控除一覧
医療費控除とは
Ⅰ 医療費控除とは あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のためにその年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の...
詳しく見る
-
控除一覧
所得から差し引かれる金額
Ⅰ 所得から差し引かれる金額とは 1.所得控除 所得控除とは、課税標準となる所得金額から一定金額を控除するものです...
詳しく見る
-
個人事業税
個人事業税の非課税事業と計算
Ⅰ 個人事業税の納税義務者とは 個人事業税の納税義務者とは、都道府県において第1種事業、第2種事業及び第3種事業を行う個...
詳しく見る
-
個人事業税
都税事務所からのお尋ね
Ⅰ都税事務所からのお尋ねについて 税務署で初めて確定申告をすると、「個人の事業内容に関する回答書」というお尋ねが届くこと...
詳しく見る
-
個人事業税
個人事業税とは
Ⅰ 個人事業税とは 個人事業税とは、個人の方が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対して係る税金(地...
詳しく見る
-
個人事業税
個人事業税FAQ
Q1 事務所又は事業所とは具体的にどういったものですか? A1 事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するもので...
詳しく見る
-
確定申告
個人が納める税金の種類
1. 所得税及び復興特別所得税 2. 消費税 3. 住民税 4. 個人事業税 5. 事業所税 6. 固定資産税 ...
詳しく見る
-
確定申告
決算書の内容
Ⅰ 青色申告者は、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかに該当する所得が生じた場合、確定申告書と合わせて決算書を提出する必要...
詳しく見る
-
確定申告
還付金とは
Ⅰ 還付金の税務上の取扱い 1.税金の課税の対象にはなりません。 2.ただし、還付金と共に還付加算金が交付された場...
詳しく見る
-
確定申告
確定申告の基礎知識
Ⅰ 確定申告とは 個人の確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入金額と経費金額より所得金額を算定し、そこ...
詳しく見る
-
確定申告
確定申告と年末調整の違いとは
Ⅰ 確定申告と年末調整の違いとは 1. 確定申告も年末調整も毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と...
詳しく見る
-
外国居住の日本人
非居住者の申告
外国に居住されている日本人は、その居住期間(または居住予定期間)が1年以上であれば、日本の所得税法上の「非居住者」に該当します...
詳しく見る
-
外国居住の日本人
非居住者の手続
日本の確定申告が必要となる人は、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果た...
詳しく見る
-
確定申告
103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁
Ⅰ これらの「壁」は、所得税あるいは社会保険料の負担が、ご本人に対して発生するかどうかを考える際、その境の目安となっている金額...
詳しく見る
-
M&A
M&Aとは
Ⅰ M&Aとは 企業の合併買収で、グローバル企業の買収以外にも中小企業でも事業承継問題で活用されています。 Ⅱ M...
詳しく見る
-
株式評価
株価評価とは
Ⅰ 取引相場のある上場株式は、取引所の株価をもって株価を評価します。 上場株式以外の株価(以下非上場株式等という)を評価...
詳しく見る
-
成年後見制度
成年後見制度
Ⅰ 成年後見制度とは、病気等により、判断能力が十分でなく、自分自身の権利を守ることができない成人の財産管理などを支援する制度で...
詳しく見る
-
信託
信託とは
Ⅰ 信託とは、委託者が自己の財産を受託者に対して受益者のために運用、管理を任せる制度です。 信託を活用した相続対策などに...
詳しく見る
-
相続関係資料
財産分割相談
Ⅰ 相続のご相談を受ける際には、相続人様の確認や相続財産の状況についてお尋ねいたします。それと同時に、分割状況も確認いたしてお...
詳しく見る
-
相続関係資料
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人がその取得する遺産について、その分割について話し合って合意した内容を記した書類です。書式は特に定まっ...
詳しく見る
-
相続関係資料
名義変更
Ⅰ 相続における名義変更とは 相続により取得した財産には、その名義変更が必要となるものがあります。 Ⅱ 不動産の名...
詳しく見る
-
相続関係資料
相続に関わる手続き
Ⅰ 相続には、不動産や預貯金、その他の動産などの様々な名義変更等、下記のような手続きが必要になります。 1.名義変更 ...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税FAQ
Q1 贈与税には110万円の基礎控除があると聞きましたが、1回の贈与につき、1年間で誰かひとりに対して110万円までなら贈与税...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税がかかる財産・かからない財産
Ⅰ 贈与税の課税価格 贈与税のかかる財産は、相続税がかかる財産とほぼ変わりません。 1.本来の贈与財産 ◆...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税の申告・納税
Ⅰ 贈与税の申告 原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに、もらった人の住所を所轄する税...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税の計算
Ⅰ 贈与税の計算及び申告 1.贈与税計算の流れ贈与税は、財産をもらった人が、その年の1月1日から12月31日までに贈与を...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与・贈与税とは
Ⅰ 贈与とは 贈与は、ある人が「あげますよ」という意思をもって、無償で自分の財産をあげることです。また、もらう側も「もら...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非...
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは、結婚・子育て資金という使途は限られますが、贈与税の非課税範...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは、教育資金という使途は限られますが、贈与者が亡くなった後も要件を満た...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税
直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度とは、住宅取得資金という使途は限られていますが、贈与税非課税で直系卑属...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除
夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するため...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
贈与税額の計算
Ⅰ 贈与税額の計算 1.相続時精算課税に係る贈与者からの贈与の場合まずは、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与...
詳しく見る
-
生前贈与による相続税対策贈与・贈与税
生前贈与による相続税対策
相続時精算課税制度が改正され、2024年1月から適用されることとなります。 これまでは活用の機会が限られていた相続時精算課税制...
詳しく見る
-
相続が発生した方
相続が発生した方(生前贈与)
相続の開始前3年以内に被相続人から財産を贈与によって取得した人は、その贈与財産の価額を相続税の課税財産に加算したうえで相続税の...
詳しく見る
-
相続が発生した方
相続が発生した方(受け取る側)
Ⅰ 遺産分割 相続税を申告・納付するにあたっては、まずは遺産を分ける手続き、いわゆる遺産分割が必要です。ご家族が亡くなっ...
詳しく見る
-
準確定申告
準確定申告とは
Ⅰ 準確定申告とは 少し聞きなれない言葉ではありますが、年の中途で死亡した人は、3月15日が提出期限の確定申告書ではなく...
詳しく見る
-
相続税
相続税FAQ
Q1 相続税には基礎控除があると聞きましたが、どのくらいの金額になるのでしょうか? A1 相続税には、法定相続人の数...
詳しく見る
-
相続税
名義財産とは
Ⅰ 名義財産 名義が親族の名義になっていて、被相続人の名義になっていなくても、実質的に所有者が被相続人であればその財産は...
詳しく見る
-
相続税
相続税の申告と流れ
Ⅰ 相続税の申告 相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した者が申告と納付をすることになります。相続の開始を知った日(亡...
詳しく見る
-
相続税
サポート体制
1.相続無料相談相続に関するあらゆるご相談をお受け致します。初回一時間無料です。 2.パートナー提携体制各種専門家(弁...
詳しく見る
-
遺言
遺言の意味
Ⅰ 遺言とは 遺言とは、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺...
詳しく見る
-
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは
Ⅰ 軽減の内容 相続等で財産を取得した配偶者は、相続税が軽減されます。 1億6000万円までか、法定相続分ま...
詳しく見る
-
小規模宅地等の特例
相続する宅地で、被相続人が住んでいた土地などには評価額...
Ⅰ 居住用宅地の減額 被相続人の居住の用に供されていた宅地を、一定の者が相続する場合、その宅地の評価額は80%減額され...
詳しく見る
-
贈与・贈与税
相続・贈与・相続税の違いとは
相続とは、個人の死亡により開始し、財産と債務の両方が移転します。手続きなしに、全財産が自動的に相続人に受け継がれます。贈与と...
詳しく見る
-
相続関係資料
相続関係資料の作成
相続税の申告においては、戸籍、土地・建物の登記簿謄本等様々な書類を取得する必要性に加え、作成しなければならない書類が多数ありま...
詳しく見る
-
相続税 かかる財産・かからない財産
相続税のかかる財産・かからない財産
Ⅰ 相続税のかからない財産とは 1.墓地、墓石、仏壇など 墓地、墓石や仏壇などは、価値判断が難しい部分もあり...
詳しく見る
-
相続税の計算
相続税の計算には、大きく分けると、三段階があります。
Ⅰ 課税価格の計算方法 相続や遺贈により財産を取得した人の各々の財産の総額を個別に計算します。 相続又遺贈により...
詳しく見る


代表税理士・スタッフブログ

スタッフブログ
2022年07月25日
お役立ち情報をリニューアルしました
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
スタッフブログをを更新しました
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
サービス情報を更新しました
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
ホームページをリニューアルしました
詳しく見る
スタッフブログ
2025年08月12日
東京都文京区
詳しく見る
スタッフブログ
2025年08月04日
やる気が出ないときは
詳しく見る
代表ブログ
2025年08月03日
日本橋茅場町事務所を開設しました。
詳しく見る
スタッフブログ
2025年08月01日
家族や友達と楽しむ隠れミッキー探し
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月28日
クラフトビールとは
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月22日
信頼は誠実な対応から生まれる
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月14日
棚卸の大切さ
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月08日
面白い本を見つけました。
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月01日
北区赤羽
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月30日
ピラティスの魅力
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月24日
暗号資産マイニング
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月16日
税理士の使命とは
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月09日
人生のカウントダウン
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月02日
ひとり老後と「死後事務委任契約」
詳しく見る
スタッフブログ
2025年05月26日
初めての海外旅行
詳しく見る
スタッフブログ
2025年05月19日
見えている世界
詳しく見る
スタッフブログ
2025年05月12日
亀戸天神の藤まつり
詳しく見る
スタッフブログ
2025年05月07日
世界で人気のキャラクターは?
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月28日
普通救命講習を受講しました
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月21日
おすすめご当地パンのご紹介
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月14日
寄席のススメ
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月07日
人を褒めるということ
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月01日
「大阪・関西万博」いよいよ開幕
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月31日
カプセルトイ
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月24日
開花宣言近し? サクラについて
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月17日
「趣味の楽しみ」
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月10日
16タイプ性格診断
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月03日
「薬師寺」
詳しく見る
スタッフブログ
2025年02月25日
新幹線の座席がなぜ2+3なのか
詳しく見る
スタッフブログ
2025年02月17日
チョコレートの効用
詳しく見る
スタッフブログ
2025年02月10日
三浦半島
詳しく見る
スタッフブログ
2025年02月03日
南瓜の豊富な栄養
詳しく見る
スタッフブログ
2025年01月28日
皇居ランニング
詳しく見る
スタッフブログ
2025年01月20日
文化の交差点ウズベキスタン
詳しく見る
スタッフブログ
2025年01月06日
江の島
詳しく見る
スタッフブログ
2024年12月23日
志摩スペイン村
詳しく見る
スタッフブログ
2024年12月16日
満月
詳しく見る
スタッフブログ
2024年12月09日
図書館利用のすすめ
詳しく見る
スタッフブログ
2024年12月02日
お菓子の話
詳しく見る
スタッフブログ
2024年11月25日
ANAのマイルで行く旅行
詳しく見る
スタッフブログ
2024年11月18日
瓦そばについて
詳しく見る
スタッフブログ
2024年11月11日
競馬の必勝法
詳しく見る
スタッフブログ
2024年11月01日
犬との生活
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月28日
第101回箱根駅伝
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月21日
新語
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月15日
Jヴィレッジでの合宿
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月08日
紅葉のおすすめスポット
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月02日
台風の名前
詳しく見る
スタッフブログ
2024年09月30日
23区の火葬事情
詳しく見る
スタッフブログ
2024年09月24日
平兵衛酢(へべす)
詳しく見る
代表ブログ
2024年09月23日
2024年基準地価発表されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2024年09月17日
2024年夏
詳しく見る
スタッフブログ
2024年09月09日
直観と反する数学
詳しく見る
2024年09月03日
水の色
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月26日
夏場の温泉について
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月19日
ご近所のお祭り
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月13日
国際左利きの日について
詳しく見る
代表ブログ
2024年08月12日
2023年度 ふるさと納税
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月05日
ハマナス
詳しく見る
代表ブログ
2024年08月02日
令和6年分路線価発表されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月01日
旧日立航空機株式会社変電所
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月29日
パリオリンピックをテレビ観戦して
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月22日
コーヒーとカフェイン
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月16日
練馬区発祥の「キャッチバレーボール」
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月08日
マイナ保険証について
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月01日
1号店
詳しく見る
スタッフブログ
2024年06月24日
ライオンキング
詳しく見る
スタッフブログ
2024年06月17日
テルマエ展
詳しく見る
スタッフブログ
2024年06月10日
サブスクリプションの普及
詳しく見る
スタッフブログ
2024年06月03日
6月の花「アジサイ」
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月27日
心にささったエピソード
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月21日
断捨離
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月13日
母の日
詳しく見る
代表ブログ
2024年05月11日
森林環境税
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月07日
ハーブティー
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月01日
富山県と私と黒部ダム
詳しく見る
スタッフブログ
2024年04月22日
右利きと左利き
詳しく見る
スタッフブログ
2024年04月15日
ハウスきゅうり栽培
詳しく見る
代表ブログ
2024年04月09日
台湾商業大学にてデジタルインボイスのシンポジウムに参加してきました。
詳しく見る
スタッフブログ
2024年04月08日
私の「推し」について
詳しく見る
スタッフブログ
2024年04月01日
エイプリルフール
詳しく見る
スタッフブログ
2024年03月26日
光速と宇宙と時間の話
詳しく見る
スタッフブログ
2024年03月21日
インターネット通販にご注意!
詳しく見る
2024年03月14日
春の花
詳しく見る
スタッフブログ
2024年03月04日
足立区綾瀬エリアと北千住のご紹介
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月27日
ドライブ
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月20日
結婚式の出来ごと
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月13日
ヨガとピラティスの違い
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月06日
流星群
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月02日
おすすめのリフレッシュ方法
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月29日
包丁研ぎ教室に参加しました
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月22日
石川県のおすすめ
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月15日
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月09日
老後は何歳からか?
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月05日
共感疲労
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月25日
ネットを利用したDIY
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月18日
冬至のかぼちゃと柚子湯
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月11日
簡単!クエン酸で疲労回復
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月04日
繊細さんの相談事
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月01日
日本三大酒どころ 西条
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月27日
UFOキャッチャー
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月20日
ラジオ
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月13日
楽しかったバス旅行
詳しく見る
代表ブログ
2023年11月13日
焼肉三千里さんのお得情報です!
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月07日
カワセミ
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月01日
3月の弥生
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月30日
セイコー・ミュージアム
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月24日
「MBTI」性格診断
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月16日
LINEのリマインド機能
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月10日
稲刈りの手伝いで帰省してきました。
詳しく見る
代表ブログ
2023年10月10日
成熟スイッチ(林真理子氏)読みました。
詳しく見る
代表ブログ
2023年10月08日
寒露(かんろ)
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月02日
VS PARKに行ってきました
詳しく見る
代表ブログ
2023年10月01日
10月 神無月(かんなづき)になりました。
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月29日
中秋の名月
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月25日
頑固おやじ
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月23日
2023年 基準地価発表されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月19日
河川敷で水遊び、上流の空模様に注意!
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月19日
書籍紹介「M&A経営論」宮原博昭氏
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月11日
2023年 東北の旅
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月11日
書籍紹介「好き嫌いで人事」松井道夫氏
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月07日
税務調査、増えてきました。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月04日
クルーズ旅行の思い出
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月03日
9月(長月)になりました。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月01日
最近買ってよかったもの
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月28日
海洋散骨をしました。
詳しく見る
代表ブログ
2023年08月24日
にちぜいくん
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月21日
仲宿
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月14日
15年前の障碍者雇用受入の思い出
詳しく見る
代表ブログ
2023年08月08日
立秋
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月07日
豊島区民です
詳しく見る
代表ブログ
2023年08月05日
令和4年度ふるさと納税
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月01日
身近なもので熱中症対策
詳しく見る
スタッフブログ
2023年07月31日
男性の日傘使用について
詳しく見る
スタッフブログ
2023年07月28日
令和5年高校生向け会社説明会を行いました
詳しく見る
2023年07月24日
ウユニ塩湖に魅せられて
詳しく見る
代表ブログ
2023年07月20日
読書感想 「好き嫌い」と経営
詳しく見る
スタッフブログ
2023年07月18日
混合治療について
詳しく見る
代表ブログ
2023年07月13日
令和5年分路線価 発表されました。Ⅱ
詳しく見る
2023年07月10日
食欲無いときにおすすめ! 梅とろろ素麺
詳しく見る
代表ブログ
2023年07月10日
千住真理子さんとストラディバリウス
詳しく見る
スタッフブログ
2023年07月04日
自治会活動
詳しく見る
代表ブログ
2023年07月04日
令和5年分路線価 発表されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月26日
モチベーションが上がるABCD
詳しく見る
代表ブログ
2023年06月21日
夏至
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月19日
冷 蔵 庫
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月12日
熱中症
詳しく見る
代表ブログ
2023年06月11日
父の日
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月05日
クラシックコンサート
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月01日
ノムさんと組織のカルチャー
詳しく見る
スタッフブログ
2023年05月29日
フレーバーティー
詳しく見る
スタッフブログ
2023年05月22日
最近気になったこと
詳しく見る
2023年05月15日
あなた その痛み本当に五十肩ですか!?
詳しく見る
2023年05月08日
光陰矢の如しと言いますが…。
詳しく見る
代表ブログ
2023年05月05日
端午の節句
詳しく見る
2023年05月01日
絵本を届ける運動
詳しく見る
代表ブログ
2023年04月30日
お客様紹介 堀口珈琲さん
詳しく見る
スタッフブログ
2023年04月24日
メタバースと税務
詳しく見る
スタッフブログ
2023年04月17日
難しい2桁の掛け算も簡単に暗算できるテクニック
詳しく見る
スタッフブログ
2023年04月10日
桜の時期になるとお腹がすきます
詳しく見る
代表ブログ
2023年04月10日
令和5年公示価格
詳しく見る
代表ブログ
2023年04月06日
うんこ税金ドリル第2弾
詳しく見る
スタッフブログ
2023年04月03日
新年度にあたり
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月27日
協会けんぽの保険料率
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月20日
池袋から北上すると・・・?
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月14日
先日あったこと。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月06日
必殺「ヤシの実割り」
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月01日
あと少し
詳しく見る
代表ブログ
2023年02月28日
お客様ご紹介 スイメイ物産さん
詳しく見る
スタッフブログ
2023年02月27日
ちょっとほっこりした話
詳しく見る
代表ブログ
2023年02月22日
2月22日 猫の日
詳しく見る
スタッフブログ
2023年02月20日
成人式という貴重な一日を守りたい。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年02月13日
旧暦の暦について
詳しく見る
代表ブログ
2023年02月04日
立春
詳しく見る
2023年02月03日
節分&恵方巻
詳しく見る
スタッフブログ
2023年02月01日
定期的に訪れたくなる場所
詳しく見る
代表ブログ
2023年02月01日
2月 如月(きさらぎ)
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月31日
「ヒト」はずっと「進化」を続けているけれど、同時に「退化」し続けている。
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月25日
令和5年税制改正大綱 電子帳簿保存制度
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月23日
自分がルールブックだ
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月18日
令和5年税制改正大綱 消費税
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月16日
Bリーグ試合観戦
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月11日
令和5年税制改正大綱 相続税・贈与税
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月10日
深海の世界
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月07日
人日(じんじつ)の節句
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月05日
調神社へ初詣
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月05日
令和5年税制改正大綱 所得税
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月04日
新年明けましておめでとうございます。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年12月26日
飯能市の紹介
詳しく見る
代表ブログ
2022年12月22日
冬至
詳しく見る
スタッフブログ
2022年12月19日
今日は何の日?
詳しく見る
スタッフブログ
2022年12月12日
悲しみの意味
詳しく見る
スタッフブログ
2022年12月12日
『笑う門には福来る』/
詳しく見る
代表ブログ
2022年12月08日
成功=ヒト×DX デジタル初心者のためのDX企業変革の教科書 読みました。
詳しく見る
代表ブログ
2022年12月06日
サッカーワールドカップ 日本チーム8強入りならず。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月30日
地方創生SDGs取組み事例のご紹介
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月28日
人前で話すことについて
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月21日
事務所周辺のお食事処
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月14日
メタバースとは
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月08日
身近なイタリア語
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月01日
新人会計事務員が考える、最も大切な資産とは
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月27日
読書週間
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月24日
終活セミナー講師してきました。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年10月24日
インボイス制度について
詳しく見る
スタッフブログ
2022年10月17日
オンデマンド研修を受講しました
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月17日
ミロク会計人会全国統一研修会
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月13日
8割を捨てて2割に集中する捨てる経営
詳しく見る
スタッフブログ
2022年10月11日
スポーツの日
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月11日
副業の税務上の扱い
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月06日
10/5日経電子版に掲載されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年10月03日
「話すチカラ」
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月01日
軽井沢 大賀ホール
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月26日
10月から変わること
詳しく見る
代表ブログ
2022年09月24日
令和4年基準地価
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月20日
親の認知症
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月12日
PARIYAさん
詳しく見る
代表ブログ
2022年09月11日
税務調査に立ち会いました。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月05日
いわき市を紹介いたします
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月02日
ことばはやさしく美しくひびきよく
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月29日
金沢カレー
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月22日
気になるテーマパーク
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月16日
カーリング
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月08日
鍵盤の日
詳しく見る
代表ブログ
2022年08月07日
令和3年度ふるさと納税 過去最高に
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月01日
茹でガエル
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月28日
世界陸上オレゴン
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月28日
夏休み2022
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
お役立ち情報をリニューアルしました
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
スタッフブログをを更新しました
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
サービス情報を更新しました
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
ホームページをリニューアルしました
詳しく見る
スタッフブログ
2025年08月12日
東京都文京区
詳しく見る
スタッフブログ
2025年08月04日
やる気が出ないときは
詳しく見る
代表ブログ
2025年08月03日
日本橋茅場町事務所を開設しました。
詳しく見る
スタッフブログ
2025年08月01日
家族や友達と楽しむ隠れミッキー探し
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月28日
クラフトビールとは
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月22日
信頼は誠実な対応から生まれる
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月14日
棚卸の大切さ
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月08日
面白い本を見つけました。
詳しく見る
スタッフブログ
2025年07月01日
北区赤羽
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月30日
ピラティスの魅力
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月24日
暗号資産マイニング
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月16日
税理士の使命とは
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月09日
人生のカウントダウン
詳しく見る
スタッフブログ
2025年06月02日
ひとり老後と「死後事務委任契約」
詳しく見る
スタッフブログ
2025年05月26日
初めての海外旅行
詳しく見る
スタッフブログ
2025年05月19日
見えている世界
詳しく見る
スタッフブログ
2025年05月12日
亀戸天神の藤まつり
詳しく見る
スタッフブログ
2025年05月07日
世界で人気のキャラクターは?
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月28日
普通救命講習を受講しました
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月21日
おすすめご当地パンのご紹介
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月14日
寄席のススメ
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月07日
人を褒めるということ
詳しく見る
スタッフブログ
2025年04月01日
「大阪・関西万博」いよいよ開幕
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月31日
カプセルトイ
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月24日
開花宣言近し? サクラについて
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月17日
「趣味の楽しみ」
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月10日
16タイプ性格診断
詳しく見る
スタッフブログ
2025年03月03日
「薬師寺」
詳しく見る
スタッフブログ
2025年02月25日
新幹線の座席がなぜ2+3なのか
詳しく見る
スタッフブログ
2025年02月17日
チョコレートの効用
詳しく見る
スタッフブログ
2025年02月10日
三浦半島
詳しく見る
スタッフブログ
2025年02月03日
南瓜の豊富な栄養
詳しく見る
スタッフブログ
2025年01月28日
皇居ランニング
詳しく見る
スタッフブログ
2025年01月20日
文化の交差点ウズベキスタン
詳しく見る
スタッフブログ
2025年01月06日
江の島
詳しく見る
スタッフブログ
2024年12月23日
志摩スペイン村
詳しく見る
スタッフブログ
2024年12月16日
満月
詳しく見る
スタッフブログ
2024年12月09日
図書館利用のすすめ
詳しく見る
スタッフブログ
2024年12月02日
お菓子の話
詳しく見る
スタッフブログ
2024年11月25日
ANAのマイルで行く旅行
詳しく見る
スタッフブログ
2024年11月18日
瓦そばについて
詳しく見る
スタッフブログ
2024年11月11日
競馬の必勝法
詳しく見る
スタッフブログ
2024年11月01日
犬との生活
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月28日
第101回箱根駅伝
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月21日
新語
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月15日
Jヴィレッジでの合宿
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月08日
紅葉のおすすめスポット
詳しく見る
スタッフブログ
2024年10月02日
台風の名前
詳しく見る
スタッフブログ
2024年09月30日
23区の火葬事情
詳しく見る
スタッフブログ
2024年09月24日
平兵衛酢(へべす)
詳しく見る
代表ブログ
2024年09月23日
2024年基準地価発表されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2024年09月17日
2024年夏
詳しく見る
スタッフブログ
2024年09月09日
直観と反する数学
詳しく見る
2024年09月03日
水の色
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月26日
夏場の温泉について
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月19日
ご近所のお祭り
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月13日
国際左利きの日について
詳しく見る
代表ブログ
2024年08月12日
2023年度 ふるさと納税
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月05日
ハマナス
詳しく見る
代表ブログ
2024年08月02日
令和6年分路線価発表されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2024年08月01日
旧日立航空機株式会社変電所
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月29日
パリオリンピックをテレビ観戦して
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月22日
コーヒーとカフェイン
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月16日
練馬区発祥の「キャッチバレーボール」
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月08日
マイナ保険証について
詳しく見る
スタッフブログ
2024年07月01日
1号店
詳しく見る
スタッフブログ
2024年06月24日
ライオンキング
詳しく見る
スタッフブログ
2024年06月17日
テルマエ展
詳しく見る
スタッフブログ
2024年06月10日
サブスクリプションの普及
詳しく見る
スタッフブログ
2024年06月03日
6月の花「アジサイ」
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月27日
心にささったエピソード
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月21日
断捨離
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月13日
母の日
詳しく見る
代表ブログ
2024年05月11日
森林環境税
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月07日
ハーブティー
詳しく見る
スタッフブログ
2024年05月01日
富山県と私と黒部ダム
詳しく見る
スタッフブログ
2024年04月22日
右利きと左利き
詳しく見る
スタッフブログ
2024年04月15日
ハウスきゅうり栽培
詳しく見る
代表ブログ
2024年04月09日
台湾商業大学にてデジタルインボイスのシンポジウムに参加してきました。
詳しく見る
スタッフブログ
2024年04月08日
私の「推し」について
詳しく見る
スタッフブログ
2024年04月01日
エイプリルフール
詳しく見る
スタッフブログ
2024年03月26日
光速と宇宙と時間の話
詳しく見る
スタッフブログ
2024年03月21日
インターネット通販にご注意!
詳しく見る
2024年03月14日
春の花
詳しく見る
スタッフブログ
2024年03月04日
足立区綾瀬エリアと北千住のご紹介
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月27日
ドライブ
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月20日
結婚式の出来ごと
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月13日
ヨガとピラティスの違い
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月06日
流星群
詳しく見る
スタッフブログ
2024年02月02日
おすすめのリフレッシュ方法
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月29日
包丁研ぎ教室に参加しました
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月22日
石川県のおすすめ
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月15日
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月09日
老後は何歳からか?
詳しく見る
スタッフブログ
2024年01月05日
共感疲労
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月25日
ネットを利用したDIY
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月18日
冬至のかぼちゃと柚子湯
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月11日
簡単!クエン酸で疲労回復
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月04日
繊細さんの相談事
詳しく見る
スタッフブログ
2023年12月01日
日本三大酒どころ 西条
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月27日
UFOキャッチャー
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月20日
ラジオ
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月13日
楽しかったバス旅行
詳しく見る
代表ブログ
2023年11月13日
焼肉三千里さんのお得情報です!
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月07日
カワセミ
詳しく見る
スタッフブログ
2023年11月01日
3月の弥生
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月30日
セイコー・ミュージアム
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月24日
「MBTI」性格診断
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月16日
LINEのリマインド機能
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月10日
稲刈りの手伝いで帰省してきました。
詳しく見る
代表ブログ
2023年10月10日
成熟スイッチ(林真理子氏)読みました。
詳しく見る
代表ブログ
2023年10月08日
寒露(かんろ)
詳しく見る
スタッフブログ
2023年10月02日
VS PARKに行ってきました
詳しく見る
代表ブログ
2023年10月01日
10月 神無月(かんなづき)になりました。
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月29日
中秋の名月
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月25日
頑固おやじ
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月23日
2023年 基準地価発表されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月19日
河川敷で水遊び、上流の空模様に注意!
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月19日
書籍紹介「M&A経営論」宮原博昭氏
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月11日
2023年 東北の旅
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月11日
書籍紹介「好き嫌いで人事」松井道夫氏
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月07日
税務調査、増えてきました。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月04日
クルーズ旅行の思い出
詳しく見る
代表ブログ
2023年09月03日
9月(長月)になりました。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年09月01日
最近買ってよかったもの
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月28日
海洋散骨をしました。
詳しく見る
代表ブログ
2023年08月24日
にちぜいくん
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月21日
仲宿
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月14日
15年前の障碍者雇用受入の思い出
詳しく見る
代表ブログ
2023年08月08日
立秋
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月07日
豊島区民です
詳しく見る
代表ブログ
2023年08月05日
令和4年度ふるさと納税
詳しく見る
スタッフブログ
2023年08月01日
身近なもので熱中症対策
詳しく見る
スタッフブログ
2023年07月31日
男性の日傘使用について
詳しく見る
スタッフブログ
2023年07月28日
令和5年高校生向け会社説明会を行いました
詳しく見る
2023年07月24日
ウユニ塩湖に魅せられて
詳しく見る
代表ブログ
2023年07月20日
読書感想 「好き嫌い」と経営
詳しく見る
スタッフブログ
2023年07月18日
混合治療について
詳しく見る
代表ブログ
2023年07月13日
令和5年分路線価 発表されました。Ⅱ
詳しく見る
2023年07月10日
食欲無いときにおすすめ! 梅とろろ素麺
詳しく見る
代表ブログ
2023年07月10日
千住真理子さんとストラディバリウス
詳しく見る
スタッフブログ
2023年07月04日
自治会活動
詳しく見る
代表ブログ
2023年07月04日
令和5年分路線価 発表されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月26日
モチベーションが上がるABCD
詳しく見る
代表ブログ
2023年06月21日
夏至
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月19日
冷 蔵 庫
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月12日
熱中症
詳しく見る
代表ブログ
2023年06月11日
父の日
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月05日
クラシックコンサート
詳しく見る
スタッフブログ
2023年06月01日
ノムさんと組織のカルチャー
詳しく見る
スタッフブログ
2023年05月29日
フレーバーティー
詳しく見る
スタッフブログ
2023年05月22日
最近気になったこと
詳しく見る
2023年05月15日
あなた その痛み本当に五十肩ですか!?
詳しく見る
2023年05月08日
光陰矢の如しと言いますが…。
詳しく見る
代表ブログ
2023年05月05日
端午の節句
詳しく見る
2023年05月01日
絵本を届ける運動
詳しく見る
代表ブログ
2023年04月30日
お客様紹介 堀口珈琲さん
詳しく見る
スタッフブログ
2023年04月24日
メタバースと税務
詳しく見る
スタッフブログ
2023年04月17日
難しい2桁の掛け算も簡単に暗算できるテクニック
詳しく見る
スタッフブログ
2023年04月10日
桜の時期になるとお腹がすきます
詳しく見る
代表ブログ
2023年04月10日
令和5年公示価格
詳しく見る
代表ブログ
2023年04月06日
うんこ税金ドリル第2弾
詳しく見る
スタッフブログ
2023年04月03日
新年度にあたり
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月27日
協会けんぽの保険料率
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月20日
池袋から北上すると・・・?
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月14日
先日あったこと。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月06日
必殺「ヤシの実割り」
詳しく見る
スタッフブログ
2023年03月01日
あと少し
詳しく見る
代表ブログ
2023年02月28日
お客様ご紹介 スイメイ物産さん
詳しく見る
スタッフブログ
2023年02月27日
ちょっとほっこりした話
詳しく見る
代表ブログ
2023年02月22日
2月22日 猫の日
詳しく見る
スタッフブログ
2023年02月20日
成人式という貴重な一日を守りたい。
詳しく見る
スタッフブログ
2023年02月13日
旧暦の暦について
詳しく見る
代表ブログ
2023年02月04日
立春
詳しく見る
2023年02月03日
節分&恵方巻
詳しく見る
スタッフブログ
2023年02月01日
定期的に訪れたくなる場所
詳しく見る
代表ブログ
2023年02月01日
2月 如月(きさらぎ)
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月31日
「ヒト」はずっと「進化」を続けているけれど、同時に「退化」し続けている。
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月25日
令和5年税制改正大綱 電子帳簿保存制度
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月23日
自分がルールブックだ
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月18日
令和5年税制改正大綱 消費税
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月16日
Bリーグ試合観戦
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月11日
令和5年税制改正大綱 相続税・贈与税
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月10日
深海の世界
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月07日
人日(じんじつ)の節句
詳しく見る
スタッフブログ
2023年01月05日
調神社へ初詣
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月05日
令和5年税制改正大綱 所得税
詳しく見る
代表ブログ
2023年01月04日
新年明けましておめでとうございます。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年12月26日
飯能市の紹介
詳しく見る
代表ブログ
2022年12月22日
冬至
詳しく見る
スタッフブログ
2022年12月19日
今日は何の日?
詳しく見る
スタッフブログ
2022年12月12日
悲しみの意味
詳しく見る
スタッフブログ
2022年12月12日
『笑う門には福来る』/
詳しく見る
代表ブログ
2022年12月08日
成功=ヒト×DX デジタル初心者のためのDX企業変革の教科書 読みました。
詳しく見る
代表ブログ
2022年12月06日
サッカーワールドカップ 日本チーム8強入りならず。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月30日
地方創生SDGs取組み事例のご紹介
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月28日
人前で話すことについて
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月21日
事務所周辺のお食事処
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月14日
メタバースとは
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月08日
身近なイタリア語
詳しく見る
スタッフブログ
2022年11月01日
新人会計事務員が考える、最も大切な資産とは
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月27日
読書週間
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月24日
終活セミナー講師してきました。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年10月24日
インボイス制度について
詳しく見る
スタッフブログ
2022年10月17日
オンデマンド研修を受講しました
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月17日
ミロク会計人会全国統一研修会
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月13日
8割を捨てて2割に集中する捨てる経営
詳しく見る
スタッフブログ
2022年10月11日
スポーツの日
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月11日
副業の税務上の扱い
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月06日
10/5日経電子版に掲載されました。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年10月03日
「話すチカラ」
詳しく見る
代表ブログ
2022年10月01日
軽井沢 大賀ホール
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月26日
10月から変わること
詳しく見る
代表ブログ
2022年09月24日
令和4年基準地価
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月20日
親の認知症
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月12日
PARIYAさん
詳しく見る
代表ブログ
2022年09月11日
税務調査に立ち会いました。
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月05日
いわき市を紹介いたします
詳しく見る
スタッフブログ
2022年09月02日
ことばはやさしく美しくひびきよく
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月29日
金沢カレー
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月22日
気になるテーマパーク
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月16日
カーリング
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月08日
鍵盤の日
詳しく見る
代表ブログ
2022年08月07日
令和3年度ふるさと納税 過去最高に
詳しく見る
スタッフブログ
2022年08月01日
茹でガエル
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月28日
世界陸上オレゴン
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月28日
夏休み2022
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
お役立ち情報をリニューアルしました
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
スタッフブログをを更新しました
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
サービス情報を更新しました
詳しく見る
スタッフブログ
2022年07月25日
ホームページをリニューアルしました
詳しく見る